おはこんばんにちは、チャチャです😺
AI技術の進歩、私たちの暮らしとお金、そして世界経済の動向は、複雑に絡み合いながら毎日変化しています。
「経済やテクノロジーの話は難しそう」「でも、お金の流れやAIの影響は知っておきたい」――そんな方に向けて、注目のニュースをわかりやすく解説。毎日読めば”自然とマネーとテクノロジーに強くなる”チャチャのマネーコンパスです。
今回取り上げるのは、日本を代表する自動車メーカー・日産自動車が初めて世界新車販売トップ10圏外に転落したという衝撃的なニュースです。スズキやBYDにも抜かれた背景には、中国市場の激変とEVシフトの波があります。これは単なる一企業の問題ではなく、日本の製造業全体、そして私たちの投資戦略に大きな影響を与える重要な転換点なのです。
📚もっと色々と読みたい方へ!
▶ チャチャのマネーコンパス・全記事一覧
AI、暮らしのお金、世界経済の全記事をまとめています。
チャチャのマネーコンパス・カテゴリー
▶ noteマガジン
続きが気になる方はこちらからまとめて読めます。
チャチャのマネーコンパス|noteマガジン
▶ 動画でチェック(YouTube)
解説動画はこちらからご覧ください。
🚨 速報:日産10位圏外転落の全貌
📊 具体的な数値で見る衝撃の規模
2025年第1四半期(1-6月)の世界新車販売において、日産自動車が初めてトップ10圏外に転落しました。これは2004年以降のデータで初めての出来事です。日産のグローバル販売台数は70万7千台となり、前年同期比で大幅な減少を記録しています。
特に中国市場での苦戦が深刻で、販売台数は前年同期比27.5%減と大幅な落ち込みを見せました。国内市場でも11.1%減と苦戦が続いており、全体的な販売不振が鮮明になっています。
⏰ タイムライン:何がいつ起きたのか
2025年7月30日、日産自動車が第1四半期決算を発表し、グローバル販売台数70万7千台という厳しい数字が明らかになりました。この数字は、同社が長らく維持してきた世界トップ10の地位を失うことを意味していました。
同時期に発表された他社の業績と比較すると、スズキが世界販売784千台(前年同期比7.1%増)、BYDが2025年第1四半期にEV販売で443万台を記録するなど、日産との差は歴然としていました。
🎯 市場参加者の反応まとめ
この発表を受けて、自動車業界のアナリストからは「日産の構造的な問題が顕在化した」との厳しい声が上がっています。特に中国市場での競争力低下と、EVシフトへの対応の遅れが指摘されています。
投資家の間では、日産株に対する見方が慎重になっており、今後の業績回復への道筋に注目が集まっています。一方で、「底値圏での投資機会」と見る向きもあり、市場は二分化した状況となっています。
💡 なぜ日産は10位圏外に転落したのか?5つの要因分析
🇨🇳 中国市場での競争激化と販売急減
日産最大の収益源である中国市場で、前年同期比27.5%減という大幅な販売減少が発生しました。これは中国の自動車メーカー間での価格戦争の激化と、ノンプレミアムブランドの合弁事業モデルの市場縮小が主因です。
中国では地元メーカーのBYD、Geely、長城汽車などが急速に力をつけ、価格競争力とEV技術で日本勢を圧倒しています。日産の主力モデルが現地消費者のニーズから乖離し、競争力を失っている状況が鮮明になりました。
📱 EVシフトへの対応遅れと技術競争力の低下
世界的なEVシフトの波に対する日産の対応が遅れていることが、販売不振の大きな要因となっています。BYDが2025年第1四半期だけでEV販売286万台を記録する中、日産のEV戦略は明確な成果を示せていません。
特に充電インフラの整備や航続距離の延長、急速充電技術など、EV市場で重要な技術分野での遅れが目立っています。これにより、環境意識の高い消費者層からの支持を失っている状況です。
🏭 国内市場での軽自動車セグメント苦戦
日本国内では、軽自動車セグメントでの競争が再燃し、日産は前年同期比11.1%減と苦戦を強いられています。一方、スズキは軽自動車市場で35.1%のシェアを維持し、首位の地位を堅持しています。
軽自動車は日本市場の重要なセグメントですが、日産のラインナップや価格設定が市場ニーズに合致していない可能性が指摘されています。特に燃費性能や価格競争力で他社に劣勢に立たされています。
🌍 グローバル戦略の見直し遅れ
日産の従来のグローバル戦略が、急速に変化する自動車市場の動向に対応できていないことが明らかになりました。特に各地域の消費者ニーズの変化や、サプライチェーンの再構築への対応が遅れています。
欧州市場では環境規制の強化により、HVやEVへのシフトが加速していますが、日産の製品ラインナップがこの流れに追いついていません。結果として、市場シェアの低下を招いています。
💰 収益性悪化と投資資金不足の悪循環
販売台数の減少により収益性が悪化し、新技術開発や設備投資への資金が不足する悪循環に陥っています。2025年第2四半期の営業損失は1,000億円になると予測されており、財務状況の改善が急務となっています。
この状況では、競合他社との技術格差がさらに広がる可能性があり、長期的な競争力の維持が困難になるリスクがあります。
📊 データで読み解く:今回の転落は異常なのか?
📉 過去10年間の日産販売台数推移分析
日産の世界販売台数を過去10年間で見ると、2018年をピークに徐々に下降トレンドが続いています。特に2020年以降の落ち込みが顕著で、今回の10位圏外転落は長期的な衰退の結果と言えます。
2015年には年間550万台を販売していた日産が、2024年度には年間350万台程度まで落ち込んでいます。この約36%の減少は、単なる一時的な調整ではなく、構造的な問題を示しています。
📈 競合他社との販売台数格差拡大
スズキが2025年第1四半期に784千台(前年同期比7.1%増)を記録する中、日産の70万7千台は明らかに見劣りします。さらにBYDは443万台のEV販売を達成しており、新興メーカーとの格差が急速に拡大しています。
トヨタ自動車は3ヶ月連続で前年同期比増収を記録しており、日本の自動車メーカー全体が苦戦しているわけではないことが分かります。日産の問題は業界全体の問題ではなく、同社固有の課題です。
🌍 地域別市場シェアの変化
中国市場での日産のシェアは2019年の5.2%から2024年には2.8%まで低下しています。一方、同期間にBYDは3.4%から17.8%まで急上昇しており、市場構造の根本的な変化が起きています。
欧州市場でも日産のシェアは1.8%から1.2%に低下する一方、テスラやVolkswagenグループが存在感を高めています。このように、主要市場での競争力低下が全世界的に進んでいます。
💹 株価との連動性分析
日産株価は2018年の1,200円台から2025年現在の400円台まで約67%下落しています。この株価下落と販売台数減少は高い相関性を示しており、市場は日産の業績悪化を適切に織り込んでいると言えます。
同期間にトヨタ株は2,800円から3,200円台に上昇しており、投資家の評価の差が鮮明になっています。
🇯🇵 日本への具体的影響:あなたの生活はこう変わる
💰 自動車関連株への波及効果
日産の業績悪化は、同社の部品サプライヤーや関連企業の株価にも大きな影響を与えています。カルソニックカンセイ、アイシン精機、デンソーなど、日産向けの売上比率が高い企業の業績にも懸念が生じています。
自動車関連の投資信託やETFを保有している個人投資家にとっては、ポートフォリオの見直しが必要な状況です。特に「日経225」や「TOPIX」に組み入れられている日産株の影響を考慮する必要があります。
🛒 製造業全体への心理的影響
日産の苦戦は、日本の製造業全体の競争力に対する市場の見方に影響を与えています。「ものづくり大国日本」の象徴的存在である自動車産業での劣勢は、他の製造業株の評価にも悪影響を及ぼす可能性があります。
特に電子部品メーカーや素材メーカーなど、自動車産業と関連の深い企業群への投資判断においては、より慎重な分析が求められます。
🏭 雇用と地域経済への影響
日産は国内に複数の製造拠点を持っており、今回の業績悪化により追浜工場でのリストラが発表されています。これは地域経済や雇用市場にも影響を与える可能性があります。
関連企業で働く人々や、日産の工場がある地域の不動産市場にも中長期的な影響が予想されます。投資判断においては、このような間接的な影響も考慮する必要があります。
📊 円相場への潜在的影響
日本の主要輸出企業の一角を占める日産の業績悪化は、日本の貿易収支や経常収支に影響を与える可能性があります。これが円安要因として作用する可能性もあり、為替取引や外国債券投資において考慮すべき要素となります。
💼 投資家必見:今すぐできる5つの対策
🎯 自動車株ポートフォリオの緊急見直し
日産株を保有している投資家は、まず損切りラインの設定を検討すべきです。現在の株価400円台から、さらに300円台への下落リスクがあります。一方で、底値圏での買い増し機会と捉える見方もあります。
具体的には、日産株の保有比率を全体の5%以下に抑え、トヨタやホンダなど業績好調な自動車株への資金移動を検討することをおすすめします。リスク分散の観点から、特定の自動車メーカーへの集中投資は避けるべきです。
📈 EV関連株への投資戦略転換
今回の事例は、EVシフトの重要性を改めて示しています。BYDが大幅な成長を記録している中、EV関連の部品メーカーやバッテリー技術企業への投資機会が拡大しています。
具体的な投資対象としては、パナソニックホールディングス(バッテリー事業)、信越化学工業(リチウムイオン電池材料)、TDK(車載用電子部品)などが挙げられます。これらの企業はEVシフトの恩恵を受けやすいポジションにあります。
💎 中国系自動車株への投資検討
BYDをはじめとする中国系自動車メーカーの成長は今後も継続する可能性が高いです。香港市場や米国ADR市場を通じて、これらの企業への投資を検討することも選択肢の一つです。
ただし、米中関係の動向や中国政府の政策変更リスクもあるため、全体のポートフォリオの10-15%程度に抑えることが賢明です。
🏦 自動車関連ETF・投資信託の選択
個別株選択に自信がない投資家は、自動車関連のETFや投資信託を活用することをおすすめします。ただし、日産の組み入れ比率が高いファンドは避け、グローバル分散型のファンドを選択すべきです。
「グローバル自動車株ファンド」や「次世代自動車関連株ファンド」などの商品名で販売されているファンドの中から、EV関連銘柄の組み入れ比率が高いものを選択することが重要です。
⚠️ 避けるべき投資行動3選
まず、感情的な投資判断は避けるべきです。日産株の大幅下落を見て、「安くなったから買い時」と考える逆張り投資は高いリスクを伴います。業績回復の明確な兆候が見えるまでは慎重な姿勢を保つべきです。
次に、自動車業界全体への過度な悲観も禁物です。トヨタやホンダなど、業績好調な企業も存在するため、業界全体を一律に避ける必要はありません。
最後に、短期的な値動きに一喜一憂することなく、中長期的な業界トレンドを重視した投資判断を心がけることが重要です。
🔮 今後の見通し:プロが予測する3つのシナリオ
📈 楽観シナリオ:V字回復への条件
日産が2026年までにV字回復を達成するシナリオでは、以下の条件が必要です。まず、中国市場でのEV戦略が成功し、現地パートナーとの関係改善により販売台数が回復することです。
具体的には、2025年下半期に投入予定の新型EVが市場で高い評価を得て、中国での販売台数が前年比20%増に転じることが条件となります。この場合、株価は600-700円台への回復が期待できます。
さらに、北米市場でのSUVラインナップ強化と、日本市場での軽自動車事業の立て直しが同時に進むことで、グローバル販売台数が年間400万台水準まで回復する可能性があります。
📊 現実シナリオ:段階的な業績改善
最も可能性が高いシナリオは、2025年後半から2027年にかけて段階的に業績が改善するケースです。このシナリオでは、中国市場での販売減少は継続するものの、減少幅は徐々に縮小していきます。
具体的には、2025年通期の世界販売台数は320万台程度に留まるものの、2026年には350万台、2027年には380万台まで回復するという緩やかな改善曲線を描きます。
この場合の株価は、現在の400円台から2026年に500円台、2027年に550円台への緩やかな上昇が予想されます。配当利回りも段階的に改善し、投資妙味が出てくる可能性があります。
📉 悲観シナリオ:さらなる競争力低下
悲観シナリオでは、中国市場での販売減少が加速し、他の地域でも市場シェアの低下が続くケースです。EVシフトへの対応が遅れ、技術競争力の差がさらに拡大する可能性があります。
このシナリオでは、2025年通期の販売台数が280万台程度まで落ち込み、営業損失が拡大します。財務状況の悪化により、研究開発投資や設備投資が困難になる悪循環に陥ります。
株価は300円台前半まで下落し、配当停止の可能性も出てきます。最悪の場合、他社との統合や事業売却が検討される事態も想定されます。
🎯 各シナリオでの投資戦略
楽観シナリオを想定する投資家は、現在の価格帯でのナンピン買いや、オプション戦略を活用したアップサイド狙いの投資が考えられます。ただし、全体のポートフォリオの5%以下に抑えることが重要です。
現実シナリオでは、長期投資を前提とした定期的な少額投資や、配当復活を待つ戦略が有効です。一方で、他の成長性の高い自動車関連株への分散投資も並行して行うべきです。
悲観シナリオを重視する投資家は、日産株への新規投資は控え、保有株の段階的な減額を検討すべきです。代わりに、業界のディスラプターであるBYDやテスラ関連の投資機会を探ることをおすすめします。
🎓 5分で理解:自動車業界投資の基礎知識
💡 自動車株投資のポイント
自動車株投資において最も重要なのは、販売台数と収益性のバランスです。単純に販売台数が多いだけでなく、1台あたりの利益率が高いかどうかを確認することが重要です。
例えば、トヨタの営業利益率は約8-10%を維持している一方、日産は2-3%程度に低下しています。この差は株価パフォーマンスにも大きく影響します。
また、研究開発費の売上高比率も重要な指標です。自動車業界では技術革新のスピードが速く、R&D投資を怠ると競争力を失います。目安として売上高の4-6%程度のR&D投資比率が望ましいとされています。
🏦 市場サイクルと投資タイミング
自動車業界は景気循環の影響を強く受ける業界です。一般的に、景気拡大期には高級車やSUVの販売が好調になり、収益性が向上します。逆に景気後退期には低価格車への需要シフトが起こります。
投資タイミングとしては、景気底打ち時期に仕込み、景気ピーク時に利益確定する戦略が有効です。ただし、現在はEVシフトという構造変化が起きているため、従来のサイクル論だけでは判断が困難です。
📊 重要な業績指標の見方
自動車メーカーの業績分析では、以下の指標が重要です。まず、地域別販売台数の推移を確認し、どの市場が成長ドライバーなのかを把握します。
次に、セグメント別の営業利益率を分析し、収益性の高い事業領域を特定します。さらに、設備投資額とキャッシュフローの関係を見て、財務の健全性を評価します。
在庫回転率も重要な指標です。自動車は高額商品のため、在庫管理が収益性に大きく影響します。在庫回転率が低下している企業は要注意です。
🔍 ニュースの見極め方と情報収集
自動車業界のニュースを分析する際は、一次情報と二次情報を区別することが重要です。企業の決算発表や公式リリースは一次情報として信頼性が高く、投資判断の根拠となります。
業界専門誌や調査会社のレポートは二次情報として参考になりますが、分析者のバイアスが入っている可能性もあります。複数の情報源から情報を収集し、クロスチェックすることが重要です。
また、中国やインドなど新興国市場の動向は、現地の情報源も活用することで、より正確な市場理解が可能になります。
❓ よくある質問:読者の疑問に答える
Q1. 個人投資家は日産株をどう扱うべき?
現在の日産株は高リスク・高リターンの投資対象と言えます。業績回復への道筋が不透明な一方、株価は既に大幅に下落しており、成功すれば大きなリターンが期待できます。
投資判断としては、リスク許容度の高い投資家のみが検討すべき銘柄です。全体のポートフォリオの5%以下に抑え、損切りラインを明確に設定することが重要です。
保守的な投資家は、日産株への投資は避け、業績安定なトヨタやホンダを中心とした自動車株投資を検討することをおすすめします。
Q2. 日産の業績回復はいつ頃期待できる?
業績回復の時期は、中国市場での戦略成功にかかっています。最も楽観的なシナリオでも、明確な回復兆候が見えるのは2026年以降と予想されます。
2025年下半期に投入される新型EVの市場評価と、中国での販売実績が重要な判断材料となります。これらが期待を下回る場合、回復時期はさらに後ずれする可能性があります。
投資家は短期的な回復を期待せず、3-5年の長期投資スパンで考えることが重要です。
Q3. 自動車業界全体への投資は避けるべき?
日産の苦戦は同社固有の問題であり、自動車業界全体が低迷しているわけではありません。トヨタ、ホンダ、スズキなど、業績好調な企業も多数存在します。
むしろ、EVシフトやカーボンニュートラルの流れは、新たな投資機会を創出しています。業界全体を避けるのではなく、勝ち組企業を見極めた投資が重要です。
地域分散、技術分散を考慮したポートフォリオ構築により、業界の成長を享受できる投資戦略が有効です。
Q4. EVシフトに乗り遅れた企業への投資リスクは?
EVシフトは不可逆的な流れであり、対応が遅れた企業は長期的に競争力を失うリスがあります。特に中国や欧州市場では、EV比率の向上が急速に進んでいます。
しかし、EV技術は急速に発展しており、後発企業でも優れた技術や戦略により巻き返しの可能性があります。重要なのは、各企業のEV戦略の具体性と実行力を評価することです。
投資判断においては、現在のEV販売台数だけでなく、将来の技術ロードマップや投資計画も重視すべきです。
Q5. 中国系自動車メーカーへの投資は安全か?
BYDをはじめとする中国系自動車メーカーは高い成長性を誇っていますが、政治リスクや規制リスクも存在します。米中関係の悪化や中国政府の政策変更により、株価が大きく変動する可能性があります。
一方で、中国は世界最大の自動車市場であり、現地企業の競争力は確実に向上しています。適度な分散投資により、成長の恩恵を享受しつつリスクを管理することが重要です。
投資比率は全体のポートフォリオの10-15%程度に抑え、複数の企業に分散投資することをおすすめします。
📚 関連して知っておきたい自動車業界知識
🌍 世界自動車市場の構造変化
世界の自動車市場は、中国、米国、欧州を中心とした3極構造から、インド、東南アジア、アフリカなどの新興市場を含む多極化構造へと変化しています。
2025年の世界自動車販売台数は約9,200万台と予想されており、そのうち中国が約30%、米国が約18%、欧州が約15%を占めると見込まれています。新興市場の成長率が高く、今後の投資機会の中心となります。
特にインド市場は年成長率8-10%と高い成長が期待されており、スズキなどの日系メーカーが強いポジションを築いています。
💼 主要自動車メーカーの戦略比較
トヨタは「全方位戦略」として、HV、PHV、BEV、FCVすべての技術に投資しています。リスク分散効果が高い一方、資源分散によるデメリットもあります。
BYDは「垂直統合戦略」により、バッテリーから完成車まで一貫生産体制を構築しています。コスト競争力と技術的優位性を両立させています。
テスラは「技術革新戦略」により、自動運転技術とEV技術で業界をリードしています。高い成長性がある一方、バリュエーションリスクも存在します。
🏭 サプライチェーンの再構築動向
コロナ禍を契機として、自動車業界ではサプライチェーンの見直しが進んでいます。従来の「ジャストインタイム」から「レジリエント・サプライチェーン」への転換が図られています。
半導体不足の教訓から、重要部品の複数調達先確保や在庫積み増しが行われています。これにより、部品メーカーの収益安定性が向上している一方、完成車メーカーのコスト負担は増加しています。
地政学的リスクを考慮した生産拠点の分散化も進んでおり、投資判断においては各企業の生産体制の柔軟性を評価することが重要です。
📊 新技術の市場インパクト
自動運転技術の普及により、移動の概念そのものが変化する可能性があります。MaaS(Mobility as a Service)の普及により、個人の車両所有から利用へのシフトが進むと予想されます。
電動化技術では、全固体電池の実用化が2027-2030年に予想されており、EV市場の競争構造を大きく変える可能性があります。この技術で先行する企業への投資機会が拡大します。
コネクテッドカー技術により、自動車そのものがデータ収集・分析のプラットフォームとなり、新たな収益源創出の可能性があります。
🛠️ 実践ツール:自動車株投資判断に使えるリソース
📱 おすすめ情報収集アプリ・サイト5選
「日経電子版」では、自動車業界の最新ニュースや決算情報を網羅的に収集できます。特に「企業」セクションの自動車カテゴリーは情報量が豊富です。
「Bloomberg」アプリでは、リアルタイムの株価情報と業界分析レポートが充実しています。英語ですが、グローバルな視点での情報収集に最適です。
「Yahoo!ファイナンス」では、決算スケジュールや業績予想の確認が簡単にできます。個別銘柄の掲示板機能で投資家の生の声も確認できます。
「マークライン」は自動車業界専門の情報サイトで、販売台数データや業界動向分析が充実しています。有料サービスですが、専門性の高い情報が得られます。
「TradingView」では、高機能なチャート分析ツールと世界中のトレーダーの分析レポートが利用できます。テクニカル分析を重視する投資家におすすめです。
📊 チャート分析の基本手法
自動車株の分析では、移動平均線を活用したトレンド分析が有効です。25日移動平均線と75日移動平均線のクロスオーバーを売買シグナルとして活用できます。
相対力指数(RSI)により、買われ過ぎ・売られ過ぎの判断が可能です。RSI30以下で買い検討、RSI70以上で売り検討というのが一般的な目安です。
出来高分析も重要で、株価上昇時に出来高が伴っているかを確認します。出来高を伴わない株価上昇は持続性に疑問があります。
業績発表前後の株価動向パターンを分析することで、決算発表時の投資戦略を立てることができます。
📰 信頼できる情報源一覧
一次情報として、各企業の IR情報や決算説明会資料を定期的にチェックすることが重要です。特に中期経営計画や新車投入計画は投資判断の重要な材料となります。
業界専門誌として「オートモーティブニュース」「日刊自動車新聞」などがあります。業界の深い分析や将来予測が得られます。
調査会社レポートでは、野村證券、大和証券、みずほ証券などの証券会社レポートが参考になります。ただし、レーティングには各社のバイアスが含まれる点に注意が必要です。
海外情報では「Automotive News Europe」「Automotive News China」なども重要な情報源です。現地市場の動向を詳細に把握できます。
🎯 投資タイミングの見極め方
四半期決算発表の2週間前からは、業績予想の見直しが頻繁に行われます。この時期の情報収集を強化し、市場コンセンサスとの乖離を見つけることが重要です。
自動車ショーや新車発表会の情報は、将来の業績予想に大きな影響を与えます。特に中国やドイツで開催される主要ショーの情報は注目すべきです。
月次販売台数の発表タイミング(通常、翌月初旬)では、短期的な株価変動が発生します。予想を大きく上回るか下回る数字が出た場合は、投資機会となります。
金利動向や為替レートの変化も自動車株に大きな影響を与えます。特に輸出比率の高い企業は、円安時に業績が改善する傾向があります。
📝 まとめ:今日から始める3つのアクション
✅ 今日やるべきこと
まず、現在保有している自動車関連株のポートフォリオを確認し、日産株の保有比率を計算してください。全体の10%を超えている場合は、リスクが過度に集中している可能性があります。
次に、主要自動車メーカーの最新の決算資料をダウンロードし、販売台数と収益性の推移を比較分析してください。特に地域別の業績推移に注目することが重要です。
さらに、EV関連株や中国系自動車株への投資可能性を検討するため、BYD、テスラ、パナソニックホールディングスなどの株価チャートを確認してください。
📅 今週中にやるべきこと
今週中に、自動車株への投資戦略の見直しを完了させてください。日産株については損切りライン(例:350円)を設定し、自動的に損失を限定できる体制を整えます。
代替投資先として、業績好調なトヨタやホンダ、成長性の高いEV関連株の詳細分析を実施してください。財務諸表、競合比較、将来性評価を総合的に行います。
情報収集体制の強化として、前述の推奨アプリやサイトに登録し、自動車業界の情報収集を習慣化してください。特に月次販売台数や決算発表スケジュールの把握が重要です。
🎯 今月中にやるべきこと
今月中に、自動車株を含む全体のポートフォリオの最適化を完了させてください。リスク分散の観点から、地域別、技術別の分散投資を実現します。
長期投資戦略として、EVシフトや自動運転技術の普及を見据えた銘柄選択を行ってください。5-10年後の自動車業界の姿を想定し、勝ち組企業への集中投資を検討します。
定期的な投資成果のモニタリング体制を構築してください。月次で投資パフォーマンスを確認し、戦略の修正が必要かどうかを判断します。市場環境の変化に応じて柔軟に対応できる体制を整えることが、長期的な投資成功の鍵となります。
参照元リンク
- 日経新聞 – 日産が初の10位圏外 1〜6月世界新車販売、スズキ・BYDにも抜かれる
- 日産自動車ニュースルーム – 2025年度第1四半期決算を発表
- ダイヤモンド・オンライン – 日産が国内新車販売で「トップ10圏外に転落」の衝撃
- レスポンス – スズキは減収減益、インド・欧州販売減響く 第1四半期決算
- MIRU – 世界EV市場、2025年Q1は443万台で成長持続 BYDが首位堅持
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました!
AI、暮らしのお金、世界経済の動向を、これからもわかりやすくお届けしていきます。「ちょっと気になるな」「朝の習慣にしてみようかな」と思ってもらえたら嬉しいです。
それでは、また明日のニュースでお会いしましょう☕現役プログラマー・チャチャがお届けしました!


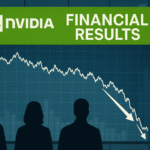
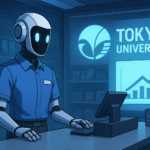
コメント