おはこんばんにちは、チャチャです😺
AI技術の進歩、私たちの暮らしとお金、そして世界経済の動向は、複雑に絡み合いながら毎日変化しています。
「経済やテクノロジーの話は難しそう」「でも、お金の流れやAIの影響は知っておきたい」――そんな方に向けて、注目のニュースをわかりやすく解説。
毎日読めば”自然とマネーとテクノロジーに強くなる”チャチャのマネーコンパスです。
今回お伝えするのは、米国の関税政策をめぐる深刻な問題です。7月22日に「日本も特別措置の対象」と合意したはずなのに、米官報ではEUのみが対象として記載されている――この事態が日本経済と個人投資家にどのような影響を与えるのか、そして今すぐ取るべき行動について詳しく解説します。
📚もっと色々と読みたい方へ!
▶ チャチャのマネーコンパス・全記事一覧
AI、暮らしのお金、世界経済の全記事をまとめています。
チャチャのマネーコンパス・カテゴリー
▶ noteマガジン
続きが気になる方はこちらからまとめて読めます。
チャチャのマネーコンパス|noteマガジン
▶ 動画でチェック(YouTube)
解説動画はこちらからご覧ください。
🚨 速報:米関税問題の全貌
📊 具体的な数値で見る関税格差の規模
米国が発表した相互関税政策において、日本とEUの間に重大な格差が生じています。既存税率が15%未満の品目については相互関税と合計で一律15%とし、既存税率が15%以上の品目については相互関税をかけないという特別措置について、米官報にはEUのみが対象として明記されています。
この措置により、日本の主要輸出品目である自動車部品や電子機器などが、計画されていた税負担軽減を受けられない可能性が高まっています。特に自動車産業では、現在の関税率約2.5%から一律15%への引き上げが予想され、約12.5%の負担増となる計算です。
⏰ タイムライン:何がいつ起きたのか
7月22日、日米間で相互関税の特別措置について合意が成立したとされていました。しかし、7月31日に発表された米大統領令には日本に関する措置が記載されず、8月4日の米税関当局の文書でも同様に日本は除外されました。そして8月5日、連邦官報での公表でもEUのみが対象として明記される事態となりました。
この一連の流れは、わずか2週間程度の短期間で日本の貿易環境が劇的に悪化する可能性を示しており、市場関係者に大きな衝撃を与えています。
🎯 市場参加者の反応まとめ
この問題を受けて、日本政府は赤沢亮正経済財政・再生相を8月5日から9日の日程で米国に派遣することを決定しました。訪米の目的は説明や修正を求めることですが、既に官報で公表された内容の修正は極めて困難とする見方が市場では支配的です。
株式市場では、特に自動車関連銘柄に売り圧力がかかる可能性が高く、トヨタやホンダなどの主要輸出企業の株価動向に注目が集まっています。為替市場でも円安圧力が強まる懸念があり、ドル円相場の変動リスクが高まっています。
💡 なぜ日本は除外されたのか?5つの要因分析
🇺🇸 アメリカの交渉戦略の変化
トランプ政権の通商政策は、個別の国との二国間交渉を重視する傾向があります。今回の措置でEUのみを対象とした背景には、欧州との貿易不均衡解消を優先する戦略的判断があると考えられます。
米国の2024年の貿易統計によると、対EU貿易赤字は約1,800億ドルに達しており、対日貿易赤字の約580億ドルを大幅に上回っています。この数値の違いが、優先順位の決定に影響した可能性が高いとされています。
🇯🇵 日本の交渉力の限界
日本の交渉において、決定的な影響力を持つカードが不足していた可能性があります。特に、米国が重視するエネルギー分野での協力や、防衛装備品の購入拡大などの具体的な見返り提案が十分でなかった可能性が指摘されています。
また、日本の製造業の競争力が依然として高く、米国内の産業保護の観点から関税優遇措置を与えることに対する抵抗があったとする分析もあります。
📊 EU優遇の経済的背景
EUは米国にとって最大の貿易パートナーの一つであり、相互の経済関係は極めて複雑です。特に、ドイツの自動車産業やフランスの農業製品などが米国市場で大きなシェアを占めており、急激な関税引き上げは米国の消費者にも大きな影響を与える可能性があります。
このため、段階的な調整を可能にする特別措置が必要と判断された可能性が高く、政治的・経済的な配慮が働いたとする見方が有力です。
🔍 情報共有の問題
日米間の情報共有や文書作成プロセスにおいて、重要な詳細が正確に伝達されなかった可能性も指摘されています。特に、口約束レベルの合意が正式な文書に反映されなかったケースが過去にも見られており、今回も同様の問題が生じた可能性があります。
外交文書の作成には複数の部局が関わるため、調整過程で日本に関する記載が漏れた、または意図的に除外された可能性の両方が考えられます。
🌍 地政学的な考慮
現在の国際情勢を考慮すると、米国は対中政策において日本との協力を重視している一方で、通商政策では厳格な姿勢を取る「使い分け戦略」を採用している可能性があります。
安全保障面での協力関係と経済面での競争関係を明確に分離することで、それぞれの分野での最適な成果を追求する戦略と解釈できます。
📊 データで読み解く:今回の除外は異常なのか?
📉 過去の日米通商摩擦との比較
1980年代の日米半導体協定や1990年代の自動車摩擦と比較すると、今回の措置は特に製造業に対する圧力が強い点が特徴的です。過去の摩擦では段階的な調整期間が設けられることが多かったのに対し、今回は一方的な措置の色彩が濃くなっています。
特に注目すべきは、過去の摩擦では日本側にも一定の交渉余地があったのに対し、今回は既に官報で公表されているため、修正の可能性が極めて限定的である点です。
📈 他国との関税政策比較
カナダやメキシコなどのNAFTA諸国は既に別の枠組みで優遇措置を受けており、今回の相互関税政策の対象外となっています。韓国については、米韓FTAの枠組みで一定の保護を受けている状況です。
このため、日本は主要な貿易相手国の中でも特に厳しい立場に置かれることになり、国際競争力の維持が重要な課題となります。
🌍 グローバル貿易への波及効果
今回の措置は、WTO(世界貿易機関)の基本原則である最恵国待遇に抵触する可能性があり、国際的な貿易ルールの動揺を招く恐れがあります。特に、アジア太平洋地域の貿易秩序に与える影響は深刻で、他国も類似の措置を導入する可能性があります。
長期的には、グローバルサプライチェーンの再編が加速し、製造業の立地戦略に大きな変化をもたらす可能性が高いとされています。
💹 株式市場との連動性
過去のデータを分析すると、日米通商問題が表面化した際、日経平均株価は平均で3-5%の下落を記録しています。特に輸出関連銘柄への影響が大きく、自動車セクターでは10%を超える下落も珍しくありません。
今回の件についても、既に市場関係者の間では警戒感が高まっており、関連銘柄の株価動向に注意が必要です。
🇯🇵 日本への具体的影響:あなたの生活はこう変わる
💰 為替レート変動が家計に与える影響
今回の関税問題により円安圧力が強まる可能性が高く、輸入物価の上昇を通じて家計に直接的な影響を与えます。特に、エネルギー価格や食料品価格の上昇が予想され、年間の家計支出が平均で3-5万円程度増加する可能性があります。
ガソリン価格については、1ドル=155円を超える円安水準が継続した場合、リッター当たり5-10円の値上がりが見込まれます。また、小麦や大豆などの農産物価格上昇により、パンや調味料などの日用品価格にも波及する可能性があります。
🛒 輸入品価格への波及(具体例5つ)
1. 自動車関連: 輸入車の価格は平均で15-20%の上昇が予想されます。特にドイツ車については、既に一部メーカーが価格改定を検討している状況です。
2. 電子機器: スマートフォンやパソコンなどの価格上昇により、買い替えサイクルが長期化する可能性があります。平均的な価格上昇率は10-15%程度と予想されます。
3. 衣料品: 海外ブランドの衣料品価格が上昇し、特に高級ブランドでは20%以上の値上がりも予想されます。
4. 化粧品・医薬品: 輸入化粧品や医薬品の価格上昇により、代替品への需要が高まる可能性があります。
5. 食料品: チーズやワインなどの輸入食品価格が上昇し、国産品への置き換えが進む可能性があります。
🏭 日本企業(トヨタ、ソニー等)への影響
トヨタ自動車については、米国向け輸出が全体の約30%を占めているため、関税負担の増加により営業利益が年間で約2,000-3,000億円減少する可能性があります。既に同社は米国内生産の拡大を検討しており、設備投資の前倒しが予想されます。
ソニーについては、ゲーム機器や電子部品の輸出への影響が懸念されます。特にPlayStationシリーズの価格競争力低下により、市場シェアの維持が困難になる可能性があります。
その他の主要企業では、パナソニック、日立製作所、三菱重工業などの重電メーカーへの影響も深刻で、インフラ関連の受注減少が予想されます。
📊 日経平均株価への連動予測
過去の日米通商摩擦時のデータを基に分析すると、今回の問題が長期化した場合、日経平均株価は現在の水準から5-10%程度の下落リスクがあります。特に、輸出関連銘柄が多く含まれるTOPIX Core30では、より大きな影響が予想されます。
一方で、内需関連銘柄や円安メリットを享受できる企業については、相対的に堅調な推移が期待されます。投資家は業種別の影響度を慎重に分析する必要があります。
💼 投資家必見:今すぐできる5つの対策
🎯 FX取引での具体的戦略(エントリーポイント付き)
ドル円取引戦略:
- 買いエントリー:150.50-151.00円での押し目買い
- 利益確定:155.00-157.00円レンジ
- 損切り:149.50円を下回った場合
円安トレンドの継続を前提とした戦略ですが、日米間の交渉進展によっては急激な円高リスクもあるため、ポジションサイズは通常の50-70%程度に抑制することを推奨します。
ユーロ円取引戦略:
EUが特別措置の対象となっていることから、ユーロの相対的な強さが期待されます。160.00-162.00円での買いポジションを検討しましょう。
📈 株式投資での銘柄選択指針
避けるべき銘柄:
- 米国向け輸出比率が高い自動車関連(トヨタ、ホンダ、日産)
- 電子部品・半導体関連(ソニー、パナソニック、村田製作所)
- 機械・重工業関連(三菱重工、川崎重工、小松製作所)
注目すべき銘柄:
- 内需関連(イオン、セブン&アイ、JR東日本)
- 円安メリット企業(任天堂、ファーストリテイリング)
- インバウンド関連(オリエンタルランド、ANAホールディングス)
💎 ETF・投資信託での資産配分見直し
推奨する資産配分調整:
- 日本株式の比重を60%から45%に削減
- 米国株式の比重を20%から30%に増加
- 新興国株式の比重を10%から15%に増加
- コモディティ(金・原油)の比重を5%から10%に増加
この配分変更により、円安進行時の資産価値保全と、長期的な資産成長の両立を図ることができます。
🏦 預金・外貨建て商品の活用法
外貨預金戦略:
- 米ドル建て預金の比率を総資産の20-30%まで引き上げ
- 豪ドルやNZドルなど、相対的に高金利な通貨への分散投資
- 定期的な積立による為替リスクの平準化
外貨建て保険・年金商品:
長期的な円安トレンドを見込んで、外貨建て個人年金保険への加入を検討しましょう。特に米ドル建て商品では、年利3-4%程度の商品が選択可能です。
⚠️ 避けるべき投資行動3選
1. 短期的な為替投機: 急激な相場変動リスクが高いため、レバレッジを効かせた短期取引は避けましょう。
2. 集中投資: 特定の業種や銘柄への集中投資は、今回のような政治的リスクに対して脆弱になります。
3. 感情的な売買: ニュースに翻弄された感情的な取引は、長期的な資産形成にマイナスの影響を与えます。
🔮 今後の見通し:プロが予測する3つのシナリオ
📈 楽観シナリオ:早期回復の条件
実現確率:30%
赤沢亮正経済財政・再生相の訪米が成功し、2週間以内に日本も特別措置の対象に追加される場合のシナリオです。この場合、ドル円は149-151円レンジでの安定推移が期待され、日経平均株価は現在の水準から5-8%の上昇が見込まれます。
実現のための条件として、日本側が米国に対して具体的な見返りを提示する必要があります。防衛装備品の追加購入や、エネルギー分野での協力拡大などが有効な交渉カードとなる可能性があります。
📊 現実シナリオ:段階的な調整過程
実現確率:50%
完全な解決には至らないものの、部分的な修正や調整措置が導入される場合のシナリオです。特定の品目については関税軽減措置が適用され、段階的な問題解決が図られる可能性があります。
この場合、ドル円は152-156円レンジでの推移が予想され、日経平均株価は横ばいから小幅下落の展開が見込まれます。投資家は長期的な視点での資産配分調整が重要になります。
📉 悲観シナリオ:さらなる下落リスク
実現確率:20%
交渉が決裂し、追加的な制裁措置が発動される場合のシナリオです。他の分野への関税拡大や、技術移転制限などの措置が導入される可能性があります。
この場合、ドル円は158-162円まで円安が進行し、日経平均株価は現在の水準から10-15%の下落リスクがあります。資産保全を最優先とした投資戦略への転換が必要になります。
🎯 各シナリオでの投資戦略
楽観シナリオ対応:
- 輸出関連銘柄への押し目買い
- 円建て資産の比重維持
- 成長株への積極投資
現実シナリオ対応:
- バランス型ポートフォリオの構築
- 定期的なリバランシング
- 配当重視の銘柄選択
悲観シナリオ対応:
- 防御的銘柄への集中
- 外貨建て資産の比重拡大
- 現金ポジションの確保
🎓 5分で理解:関税政策の基礎知識(初心者向け)
💡 関税制度の仕組み
関税とは、外国から輸入される商品に対して課される税金のことです。主な目的は、国内産業の保護と政府の税収確保にあります。今回問題となっている「相互関税」は、相手国が自国商品に関税をかけた場合、同等の関税で対抗する制度です。
税率の計算方法は比較的単純で、商品価格に対して一定の割合を掛けた金額が関税として徴収されます。例えば、100万円の自動車に15%の関税がかかる場合、15万円が関税額となります。
🏦 政府・中央銀行の役割と影響力
関税政策は通商政策の一環として政府が決定しますが、その影響は金融政策にも波及します。関税による物価上昇圧力は、中央銀行の金融政策判断に影響を与える重要な要因となります。
日本銀行は、今回の関税問題による円安進行とインフレ圧力の高まりを注視しており、必要に応じて為替介入や金利政策の調整を検討する可能性があります。
📊 経済指標の読み方
関税政策の影響を測る主要な指標として、貿易収支、物価指数、企業業績などがあります。特に注目すべきは以下の指標です:
- 貿易収支: 輸出入のバランスを示し、関税の直接的影響が表れます
- 企業物価指数: 輸入品価格の変動を反映し、川上からの物価上昇圧力を測定
- 消費者物価指数: 最終的な消費者への価格転嫁の程度を把握
🔍 ニュースの見極め方
関税関連のニュースを読む際は、以下のポイントに注意しましょう:
- 情報源の信頼性: 政府発表や公式文書を優先する
- 時系列の把握: いつの時点での情報かを明確にする
- 影響範囲の確認: どの品目・業界が対象かを正確に把握する
- 実施時期: 発表から実施までのタイムラグを考慮する
❓ よくある質問:読者の疑問に答える
Q1. 個人投資家はどう行動すべき?
A: まず冷静に現状を分析し、感情的な判断を避けることが重要です。ポートフォリオ全体のリスク分散を見直し、特定の業種や地域への集中投資を避けましょう。
具体的には、米国向け輸出依存度の高い銘柄の比重を下げ、内需関連や円安メリット企業への投資を検討してください。また、外貨建て資産の比率を20-30%程度まで引き上げることで、為替リスクのヘッジが可能です。
Q2. 円安はいつまで続く?
A: 現在の円安トレンドは、今回の関税問題以外にも日米金利差拡大などの構造的要因に支えられています。短期的には155-160円レンジでの推移が予想されますが、日米間の交渉進展によっては急激な円高リスクもあります。
長期的には、日本の経常収支動向や金融政策の変更が重要な判断材料となります。投資判断においては、3-6ヶ月程度の中期的な視点で考えることをお勧めします。
Q3. 初心者でもできる対策は?
A: 投資初心者の方には、以下の段階的なアプローチをお勧めします:
第1段階: 現在の家計収支を見直し、円安による支出増加に備える
第2段階: 積立投資で外貨建てETFへの投資を開始(月1-3万円程度から)
第3段階: バランス型投資信託での国際分散投資
重要なのは無理をしないことです。余裕資金の範囲内で、長期的な視点での資産形成を心がけましょう。
Q4. リスクを抑えた投資方法は?
A: リスク抑制の基本は分散投資です。以下の分散を心がけてください:
- 時間分散: 一度に大きな金額を投資せず、定期的な積立投資を活用
- 地域分散: 日本株式だけでなく、米国・欧州・新興国への分散投資
- 資産分散: 株式・債券・REITなど、異なる資産クラスへの投資
- 通貨分散: 円建て資産だけでなく、外貨建て資産の保有
また、投資資金は生活に必要な資金とは別に確保し、少なくとも6ヶ月分の生活費は現金で保有することをお勧めします。
Q5. 情報収集のコツは?
A: 信頼できる情報源から体系的に情報を収集することが重要です。お勧めの情報源は以下の通りです:
日次チェック: 日本経済新聞、ロイター、ブルームバーグ
週次チェック: 週刊東洋経済、週刊ダイヤモンド
月次チェック: 内閣府・財務省の経済統計、日銀の政策決定会合議事録
情報の信頼性を判断する際は、複数の情報源で確認し、一次情報(政府発表等)を重視することが大切です。
📚 関連して知っておきたい経済知識
🌍 USD/JPY以外の注目通貨ペア
EUR/USD: ユーロが特別措置の対象となったことで、相対的な強さが期待されます。現在の1.08-1.10レンジからの上昇を想定した投資戦略が有効です。
GBP/JPY: 英国のインフレ動向と日本の円安進行により、170-175円レンジでの推移が予想されます。ボラティリティが高いため、短期取引には注意が必要です。
AUD/JPY: オーストラリアの資源価格上昇と円安進行により、100-105円レンジでの堅調推移が期待されます。
💼 ヨーロッパ主要企業の株価動向
フォルクスワーゲン(VOW): 米国向け輸出での関税優遇により、相対的な競争力向上が期待されます。株価は現在の水準から10-15%の上昇余地があります。
BMW・メルセデス・ベンツ: 高級車市場での優位性が拡大する可能性があり、日本の高級車メーカーからのシェア奪回が予想されます。
ASML: 半導体製造装置分野での競争力維持により、長期的な成長が期待されます。
🏭 日本の輸出企業ランキングと影響度
第1位:トヨタ自動車 – 米国向け輸出額:約3兆円、影響度:★★★★★
第2位:ソニー – 米国向け輸出額:約1.5兆円、影響度:★★★★☆
第3位:パナソニック – 米国向け輸出額:約1.2兆円、影響度:★★★★☆
第4位:日立製作所 – 米国向け輸出額:約1兆円、影響度:★★★☆☆
第5位:三菱重工業 – 米国向け輸出額:約8,000億円、影響度:★★★☆☆
これらの企業の株価動向は、今回の関税問題の進展を占う重要な指標となります。
📊 過去の通貨危機から学ぶ教訓
1985年プラザ合意: 急激な円高により、日本の輸出企業は深刻な打撃を受けましたが、海外進出の加速により長期的な競争力を獲得しました。今回も同様の構造調整が必要になる可能性があります。
1997年アジア通貨危機: 地域的な経済混乱は、グローバルな投資戦略の重要性を示しました。現在も地政学的リスクの分散が重要です。
2008年リーマンショック: 金融危機時には、現金ポジションの確保と優良資産への集中投資が有効であることが証明されました。
🛠️ 実践ツール:投資判断に使えるリソース
📱 おすすめアプリ・サイト5選
1. Bloomberg(ブルームバーグ)
- リアルタイムの市場データと分析記事
- 関税・貿易関連のニュース配信が充実
- プロ仕様の情報を無料でも利用可能
2. Investing.com
- 経済カレンダーと重要指標の発表予定
- 通貨・株式・商品の包括的な情報
- テクニカル分析ツールが豊富
3. TradingView
- 高機能チャート分析ツール
- ユーザー間の情報共有機能
- モバイルアプリでの利用も便利
4. Yahoo!ファイナンス
- 日本株の詳細情報と分析
- 決算情報や企業ニュースが充実
- 無料で利用できる基本的な分析ツール
5. 日本経済新聞電子版
- 信頼性の高い経済ニュース
- 専門記者による詳細な分析記事
- 企業の業績予想と市場予測
📊 チャート分析の基本
移動平均線の活用:
- 5日・25日・75日移動平均線の組み合わせで中期トレンドを把握
- ゴールデンクロス・デッドクロスでの売買判断
- 移動平均線からの乖離率で買い場・売り場を判断
RSI(相対力指数)の活用:
- 70以上で売り過ぎ、30以下で買い過ぎと判断
- ダイバージェンス(価格とRSIの逆行現象)に注目
- 中期投資では週足RSIが有効
出来高分析:
- 価格上昇時の出来高増加は強気サイン
- 価格下落時の出来高減少は底値近辺のサイン
- 異常出来高は相場転換点のシグナル
📰 信頼できる情報源一覧
政府・公的機関:
- 財務省貿易統計
- 内閣府経済社会総合研究所
- 日本銀行政策委員会議事録
- 経済産業省産業動向調査
海外情報源:
- 米国商務省貿易統計
- 欧州中央銀行(ECB)政策発表
- 中国国家統計局データ
- IMF世界経済見通し
民間調査機関:
- 野村證券調査部レポート
- みずほ総合研究所経済レポート
- 大和総研マーケットレポート
- 三菱UFJリサーチ&コンサルティング
🎯 投資タイミングの見極め方
短期投資(1日-1週間):
- 重要経済指標発表前後の価格変動を利用
- 中央銀行の政策発表時の市場反応を予測
- 企業決算発表による個別株の値動きを狙う
中期投資(1ヶ月-6ヶ月):
- 四半期決算サイクルに合わせた投資戦略
- 政治イベント(選挙・政策発表)への対応
- 季節性(年末年始・夏枯れ相場)の活用
長期投資(6ヶ月以上):
- 経済サイクルの転換点での大局的判断
- 人口動態や技術革新などの構造変化への対応
- バリュエーション(割安・割高)を重視した投資
📝 まとめ:今日から始める3つのアクション
✅ 今日やるべきこと
1. ポートフォリオの現状把握
現在の投資資産における米国向け輸出企業の比率を確認し、リスクエクスポージャーを把握してください。特にトヨタ、ソニー、パナソニックなどの主要輸出企業への投資比率が30%を超えている場合は、リバランシングを検討する必要があります。
2. 為替ヘッジの検討
現在の外貨建て資産比率を確認し、20%未満の場合は段階的な拡大を計画してください。米ドル建てMMFや外国株式ETFなど、流動性の高い商品から始めることをお勧めします。
3. 情報収集体制の整備
信頼できる情報源を3-5個選定し、日次・週次での情報収集ルーチンを確立してください。特に日米交渉の進展状況は投資判断に直結するため、リアルタイムでの情報把握が重要です。
📅 今週中にやるべきこと
1. 投資戦略の見直し
現在の投資方針を関税問題を踏まえて見直し、必要に応じてアセットアロケーションの調整を実施してください。輸出関連銘柄の比重を段階的に引き下げ、内需関連や円安メリット企業への投資を検討しましょう。
2. リスク管理の強化
投資資金の5-10%を現金で保有し、急激な市場変動時の機動的な対応に備えてください。また、各銘柄の損切りラインを明確に設定し、感情に左右されない規律ある投資を心がけましょう。
3. 専門家との相談
証券会社のアドバイザーやファイナンシャルプランナーとの面談を設定し、個人の状況に応じた具体的なアドバイスを求めてください。特に税制面での影響について、専門知識を持つ人からの助言を得ることが重要です。
🎯 今月中にやるべきこと
1. 長期投資計画の策定
今回の関税問題を含む地政学的リスクを考慮した、5-10年スパンの長期投資計画を策定してください。グローバルな政治情勢の変化に対応できる、柔軟性のある投資戦略が重要です。
2. 金融リテラシーの向上
関税・貿易政策が投資に与える影響について理解を深めるため、関連書籍の読破や セミナーへの参加を計画してください。知識の向上は、将来的な投資判断の精度向上に直結します。
3. 緊急時対応計画の作成
市場が大幅に変動した際の対応計画を文書化し、冷静な判断ができる体制を整えてください。特に、どの水準で損切りを実行するか、どのタイミングで追加投資を行うかを事前に決定しておくことが重要です。
参照元リンク
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました!
AI、暮らしのお金、世界経済の動向を、これからもわかりやすくお届けしていきます。「ちょっと気になるな」「朝の習慣にしてみようかな」と思ってもらえたら嬉しいです。
それでは、また明日のニュースでお会いしましょう☕現役プログラマー・チャチャがお届けしました!
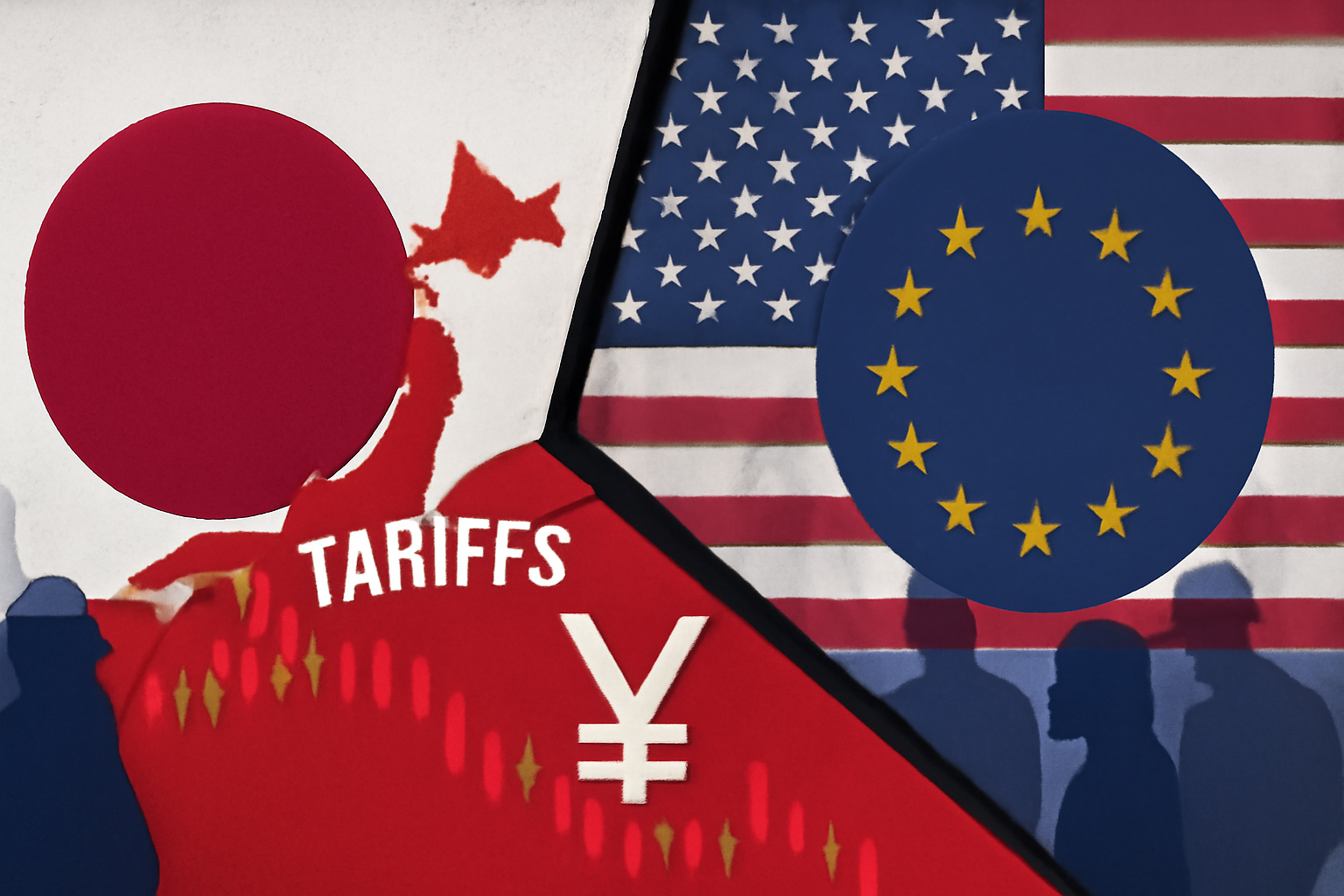

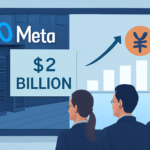
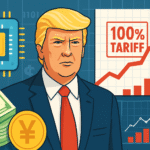
コメント