おはこんばんにちは、チャチャです😺
AI技術の進歩、私たちの暮らしとお金、そして世界経済の動向は、複雑に絡み合いながら毎日変化しています。
「経済やテクノロジーの話は難しそう」「でも、お金の流れやAIの影響は知っておきたい」――そんな方に向けて、注目のニュースをわかりやすく解説。
毎日読めば”自然とマネーとテクノロジーに強くなる”チャチャのマネーコンパスです。
日立製作所の白物家電事業売却検討という今回のニュースは、日本の産業構造の変化と投資家の資産戦略に重要な示唆を与えています。韓国・サムスン電子が買収に意欲を示すこの動きは、単なる企業買収を超えて、日本の製造業の未来と個人投資家の投資判断に直結する重要な転換点となります。
📚もっと色々と読みたい方へ!
▶ チャチャのマネーコンパス・全記事一覧
AI、暮らしのお金、世界経済の全記事をまとめています。
チャチャのマネーコンパス・カテゴリー
▶ noteマガジン
続きが気になる方はこちらからまとめて読めます。
チャチャのマネーコンパス|noteマガジン
▶ 動画でチェック(YouTube)
解説動画はこちらからご覧ください。
🚨 速報:日立白物家電売却の全貌
日立製作所が国内白物家電事業を手がける子会社・日立グローバルライフソリューションズ(GLS)の売却を検討していることが2025年8月4日に明らかになりました。これは日立グループの大規模な構造改革の一環として位置づけられており、鉄道や電力などの高収益事業への経営資源集中を目指す戦略的判断です。
📊 具体的な数値で見る売却の規模
日立GLSは冷蔵庫や洗濯機など白物家電の国内市場で重要なポジションを占めています。売却価格については現時点で公表されていませんが、同規模の家電事業買収では数千億円規模の取引となることが予想されます。日立の白物家電事業は年間数百億円の売上規模を持つ事業部門であり、買収企業にとっても大型投資案件となります。
⏰ タイムライン:何がいつ起きたのか
- 8月4日:韓国経済紙「毎日経済」が売却検討を初報
- 10月予定:優先交渉権を与える企業の絞り込み
- 12月予定:最終的な売却先の決定
このスケジュールから見ると、年内に売却が完了する可能性が高く、来年度の日立の業績に大きな影響を与えることが予想されます。
🎯 市場参加者の反応まとめ
韓国メディアの報道によると、サムスン電子が最も積極的な買収意欲を示しており、LG電子も関心を表明しています。さらに、トルコや中国の企業も買収候補として名前が挙がっています。複数の企業が競合することで、売却価格の上昇も期待される状況です。
💡 なぜ日立は白物家電を売却するのか?5つの要因分析
日立製作所の白物家電事業売却は単なる事業整理ではなく、複雑な経営環境の変化に対応した戦略的判断です。この決定には、グローバル競争の激化、収益構造の変化、技術革新のスピード、そして日本市場の構造的変化という多層的な要因が影響しています。これらの要因を深く理解することで、日本の製造業全体が直面する課題と今後の方向性も見えてきます。
🎯 選択と集中戦略の加速:高収益事業への経営資源の全面投入
日立の「選択と集中」戦略は2010年代から段階的に推進されてきましたが、近年その動きは一層加速しています。同社が中核事業として位置づけているのは、電力・エネルギー、鉄道システム、産業・流通・水道、ビルシステムという4つの事業領域です。これらの事業は共通して社会インフラという特性を持ち、高い参入障壁と安定した収益性を確保できる分野です。
白物家電事業の営業利益率は業界平均で約3-5%程度に留まる一方、日立の社会インフラ事業は10%以上の高い利益率を維持しています。この差は単なる数字以上の意味を持ちます。社会インフラ事業では長期契約が基本であり、メンテナンスやアップグレードによる継続的な収益が見込めるのに対し、白物家電は製品販売による一回限りの収益モデルです。
さらに重要なのは、日立が成長戦略の柱とするデジタル基盤「ルマーダ」との親和性です。ルマーダは IoT、AI、ビッグデータを活用して顧客の課題解決を行うプラットフォームですが、白物家電事業とのシナジー効果は限定的でした。電力システムや鉄道システムでは、ルマーダによる運行最適化や予防保全によって顧客に大きな価値を提供できますが、家電製品では そこまでの付加価値創造は困難でした。
投下資本収益率(ROIC)の観点でも、白物家電事業は製造設備や在庫に大きな資本を必要とする割に、リターンが限定的です。一方、ソフトウェアやサービス中心の事業では、より少ない資本でより高いリターンを得ることができます。日立は限られた経営資源を最も効率的に活用するために、この戦略的選択を行ったのです。
📉 国内市場の構造的な縮小:人口動態が示す厳しい現実
日本の白物家電市場は人口減少と高齢化という構造的要因により、避けられない縮小過程にあります。総務省の統計によると、日本の世帯数は2020年をピークに減少に転じ、2040年には現在より約400万世帯減少すると予測されています。新規世帯の形成数減少は、冷蔵庫や洗濯機といった生活必需品家電の新規需要に直接的なマイナス影響を与えます。
さらに深刻なのは、既存世帯における買い替えサイクルの長期化です。技術の成熟化により家電製品の耐久性が向上し、消費者の使用期間が延長されています。冷蔵庫の平均使用年数は10年前の8.9年から現在は11.2年に延び、洗濯機も7.8年から9.1年に延長しています。この傾向は今後も続くと予想され、市場規模の自然減に拍車をかけています。
高齢化も市場縮小の大きな要因です。65歳以上の高齢者は一般的に家電の購入頻度が低く、機能よりも操作の簡便性を重視する傾向があります。また、高齢者世帯では家電に対する支出額も若年世帯より約30%低いという調査結果もあります。2040年には日本の高齢化率が35%を超えることが予想されており、市場の成熟化は避けられない状況です。
地方過疎化の進行も見逃せない要因です。人口流出により地方の家電販売店が閉店するケースが増えており、販売チャネルの縮小も市場規模に影響を与えています。都市部への人口集中は住宅の狭小化を促し、大型家電の需要減少にもつながっています。
これらの構造的変化は短期的な景気変動とは異なり、根本的かつ長期的な市場環境の悪化を意味します。企業がいくら努力しても変えられない外部要因であるため、事業戦略の根本的な見直しが不可欠となったのです。
🌏 グローバル競争の激化:技術優位性の喪失と価格競争の現実
かつて日本の家電メーカーが誇った技術的優位性は、近年急速に失われています。特に韓国と中国のメーカーの技術力向上は目覚ましく、多くの分野で日本メーカーと同等かそれ以上の性能を持つ製品を、より低価格で提供できるようになりました。
韓国企業の技術革新は特に注目に値します。サムスン電子は年間売上の約7%を研究開発に投資し、AI搭載冷蔵庫や音声認識洗濯機など、次世代家電の開発で先行しています。LG電子も同様に、有機ELディスプレイ技術を家電に応用するなど、技術的な差別化を図っています。これらの企業は日本企業よりもスマートフォンやディスプレイ事業で培った先進技術を家電に転用する能力に優れており、イノベーションのスピードでも上回っています。
中国企業のコストパフォーマンスも脅威となっています。ハイアール、美的集団、海信といった中国大手は、巨大な国内市場を背景とした規模の経済性により、同等品質の製品をより安価に提供できます。中国の製造業は「世界の工場」から「世界の開発拠点」へと進化しており、単純な価格競争だけでなく、技術開発力でも急速に追い上げています。
グローバル市場でのシェア変化も日本企業には厳しい現実を突きつけています。世界の白物家電市場における日本企業のシェアは2010年の約15%から2020年には約8%まで低下し、代わって中国企業が約40%、韓国企業が約20%のシェアを獲得しています。特に冷蔵庫市場では中国のハイアールが世界トップシェアを握り、洗濯機市場でもアジア系企業が上位を占めています。
ブランド力の変化も見逃せません。かつて「Made in Japan」は品質の代名詞でしたが、現在は韓国や中国のブランドも同等の品質認識を獲得しています。特に若年層では、機能性や価格を重視する傾向が強く、日本ブランドへの特別な愛着は薄れています。
この状況下で日本の家電メーカーが競争力を維持するためには、従来の量産効果による価格競争ではなく、全く異なる価値提案が必要となります。しかし、これは限られた経営資源では困難であり、より競争優位性の高い事業領域への集中が合理的な判断となるのです。
💰 キャッシュフロー改善の必要性:資本効率性の根本的課題
白物家電事業は資本集約型事業の典型であり、継続的な設備投資と大量の運転資金を必要とします。製造設備は技術革新に対応するため定期的な更新が必要で、年間売上の5-8%程度の設備投資が常に発生します。また、季節変動に対応するための在庫保有、部品調達のための前払い、販売代理店への与信管理なども大きな資金需要を生みます。
キャッシュコンバージョンサイクル(現金を投じてから回収するまでの期間)の観点では、白物家電事業は非効率性が目立ちます。原材料の調達から製品の完成、販売、代金回収まで通常4-6ヶ月を要し、この間の資金は収益を生まない状態で固定されます。一方、日立が注力する IT サービス事業では、人的資源が主な投入要素であり、キャッシュフローのタイミングがより良好です。
収益の変動性も重要な課題です。家電需要は経済情勢や気候変動に左右されやすく、売上の予測が困難です。特に日本市場では、消費税増税や自然災害などの外的要因によって需要が急激に変動するケースが頻繁に見られます。このような収益の不安定性は、長期的な事業計画の策定を困難にし、投資家からの評価も低下させます。
競争激化による価格下落圧力も深刻です。新興国メーカーとの価格競争により、製品単価は継続的に下落しており、同じ販売数量でも売上は減少する構造的問題があります。価格下落を補うためには販売数量の大幅な増加が必要ですが、市場全体が縮小する中では現実的ではありません。
さらに、環境規制への対応コストも増加しています。省エネ基準の厳格化、リサイクル法への対応、化学物質規制など、コンプライアンス関連の投資が年々増加し、収益性を圧迫しています。これらの投資は法的義務であるため削減できず、事業の収益構造改善を困難にしています。
日立の経営陣は、これらの資本効率性の問題を根本的に解決するため、より資本効率の良い事業への転換を決断しました。社会インフラ事業では、初期投資は大きいものの、長期間にわたる安定した収益により投資回収が確実で、キャッシュフロー・プロファイルも優れています。
🔄 事業ポートフォリオの最適化:未来への投資戦略
日立の事業ポートフォリオ戦略は、単純な不採算事業の切り離しを超えて、デジタル変革時代に適応した企業への変貌を目指しています。同社は 2021年に策定した中期経営計画で「デジタルでつながる社会インフラ企業」というビジョンを掲げ、この実現のための事業構造改革を進めています。
ルマーダエコシステムの拡大が最重要戦略です。ルマーダは単なる技術プラットフォームではなく、顧客企業のデジタル変革を支援する包括的なソリューションです。電力事業では発電効率の最適化、鉄道事業では運行管理の高度化、産業機器では予防保全の自動化など、各事業領域でルマーダを活用した高付加価値サービスを提供しています。白物家電事業からの撤退により、これらの成長領域により多くの経営資源を投入できるようになります。
社会課題解決型ビジネスモデルへの転換も重要な要素です。気候変動対応、都市化による交通渋滞解消、高齢化社会のインフラ維持など、社会が直面する課題は日立の事業機会でもあります。これらの課題は長期的かつ継続的な取り組みが必要で、一度構築した関係は長期間継続する傾向があります。この特性により、安定した収益基盤を構築できます。
グローバル市場での競争ポジションも考慮要因です。社会インフラ事業では、日立は世界的に高い技術力と実績を持ち、競合他社に対する優位性があります。特に鉄道システムでは欧州市場で高い評価を得ており、電力システムでも再生可能エネルギー関連技術で先行しています。これに対し、白物家電事業では前述の通り競争劣位に置かれており、グローバル展開の将来性が限定的でした。
株主価値の最大化という観点でも、この戦略転換は合理的です。高成長・高収益事業への集中により、PERやROEなどの財務指標の改善が期待でき、株価の持続的な上昇につながります。実際、類似の戦略転換を行った他社では、短期的な売上減少にも関わらず、利益率の改善により株価が上昇するケースが多く見られます。
人材リソースの最適活用も重要な考慮事項です。白物家電事業で培った製造技術や品質管理のノウハウは、産業機器や社会インフラ機器の製造にも活用できます。優秀な技術者や管理者を、より成長性の高い事業領域に配置転換することで、組織全体の生産性向上も期待できます。
この事業ポートフォリオの最適化により、日立は「総合電機メーカー」から「社会イノベーション事業のグローバルリーダー」への転換を目指しています。白物家電事業の売却は、この壮大な変革プロジェクトの重要な一歩なのです。
📊 データで読み解く:今回の売却は異常なのか?
日立の白物家電売却を過去の企業買収や事業売却と比較することで、この動きの位置づけを明確にできます。
📈 過去の日本企業による事業売却事例
近年、日本企業による非中核事業の売却は活発化しています。東芝の白物家電事業は2016年に中国の美的集団に売却され、シャープは2016年に台湾の鴻海精密工業に買収されました。これらの事例と比較すると、日立の動きは日本製造業の構造転換の一環として理解できます。
💹 売却による企業価値への影響分析
過去の事例では、非中核事業の売却は短期的には株価にプラス要因として働くことが多く見られます。東芝の白物家電売却時は売却発表後に株価が上昇し、投資家から戦略的判断として評価されました。日立についても同様の反応が期待されます。
🌍 韓国企業による日本企業買収の動向
韓国企業による日本企業や日本事業の買収は2010年代以降増加傾向にあります。サムスン電子やLG電子は技術力強化と市場拡大を目的とした買収を積極的に行っており、日立の白物家電事業もこの流れの延長線上にあります。
📊 白物家電業界の市場再編
グローバルな白物家電市場では、中国のハイアールや韓国のサムスン・LGなど大手企業による市場統合が進んでいます。日立の売却もこの業界再編の一部として捉えることができ、より効率的な市場構造への移行を意味しています。
🇯🇵 日本への具体的影響:あなたの生活はこう変わる
日立の白物家電事業売却は、日本の消費者や経済に多面的な影響を与えることが予想されます。
💰 家電製品価格への影響予測
買収後の価格戦略次第では、消費者にとって製品価格に変化が生じる可能性があります。韓国企業は一般的にコストパフォーマンスを重視する傾向があり、同等性能でより安価な製品の提供が期待できる一方、高級路線では価格上昇の可能性もあります。
🛒 製品ラインナップと技術革新
サムスン電子やLG電子は AI搭載家電やスマートホーム技術で先進的な取り組みを行っており、日立ブランドの製品にもこれらの技術が導入される可能性が高まります。消費者はより高機能で便利な家電製品を利用できるようになることが期待されます。
🏭 日本国内の雇用への影響
売却に伴う雇用への影響は重要な関心事項です。過去の類似ケースでは、買収企業が既存の研究開発拠点や製造拠点を維持するケースが多く、大規模な人員削減は限定的でした。むしろ、新技術導入により雇用の質の向上が期待されます。
📊 関連産業への波及効果
白物家電の部品供給企業や販売代理店など、関連産業への影響も考慮する必要があります。買収企業の調達方針や販売戦略の変更により、これらの企業の業績にも影響が生じる可能性があります。
💼 投資家必見:今すぐできる5つの対策
日立の白物家電売却ニュースを受けて、投資家が取るべき具体的な行動戦略を提示します。
🎯 日立製作所株への投資戦略
売却による事業効率化は日立の株価にとってプラス要因と考えられます。売却完了後の収益性向上を見込んで、中長期的な投資を検討する価値があります。ただし、売却価格や売却資金の使途に注目し、詳細な計画が明らかになってから投資判断を行うことが重要です。
📈 関連銘柄の投資機会分析
日立の構造改革により恩恵を受ける可能性の高い関連銘柄に注目しましょう。電力事業関連では東芝エネルギーシステムズ、鉄道事業では川崎重工業などが競合企業として相対的に優位に立つ可能性があります。
💎 韓国株式市場への投資検討
サムスン電子やLG電子への投資も検討に値します。日立の白物家電事業買収により、これら企業の日本市場での競争力強化が期待されます。特にサムスン電子は多角化戦略の一環として、この買収を成長の原動力とする可能性があります。
🏦 家電関連ETFの活用
個別銘柄選択が困難な場合は、家電関連ETFへの投資を検討しましょう。業界全体の再編による効率化の恩恵を受けることができます。また、アジア太平洋地域の家電企業に分散投資できるETFも選択肢となります。
⚠️ 避けるべき投資行動3選
- 短期的な値動きでの売買:M&Aニュースは短期的な価格変動を引き起こしやすいため、感情的な取引は避けるべきです。
- 情報不足での投資:売却価格や条件が明確になる前の性急な投資判断は危険です。
- 単一銘柄への集中投資:業界再編期には予期しない変動が起こりやすいため、分散投資を心がけましょう。
🔮 今後の見通し:プロが予測する3つのシナリオ
日立白物家電売却の行方と市場への影響について、3つの可能性を検討します。
📈 楽観シナリオ:サムスン買収による相乗効果最大化
サムスン電子が買収に成功し、両社の技術とブランド力を活かした新製品開発が順調に進むシナリオです。日立は売却資金を高収益事業に集中投資し、ROEの大幅な改善を実現します。サムスン側も日本市場での地位を確立し、両社がwin-winの関係を築きます。
このシナリオでは、日立株価は15-20%程度の上昇が期待され、サムスン電子も中長期的な成長ストーリーが市場に評価される可能性があります。
📊 現実シナリオ:段階的な統合による安定的成長
買収完了後、段階的な事業統合が進み、2-3年をかけて相乗効果が徐々に現れるシナリオです。日立は売却資金を慎重に配分し、リスクを抑えながら事業転換を進めます。市場の反応は穏やかで、株価は5-10%程度の上昇に留まります。
このシナリオが最も確率が高く、投資家にとっては安定的なリターンが期待できる展開となります。
📉 悲観シナリオ:統合の困難とブランド価値毀損
買収後の事業統合が難航し、日立ブランドの価値が十分に活かされないシナリオです。売却価格が期待を下回ったり、買収企業側の戦略が不明確だった場合に起こる可能性があります。
このシナリオでは、日立株価への影響は限定的か、場合によってはマイナスとなる可能性もあります。投資家は慎重な姿勢で状況を見守る必要があります。
🎓 5分で理解:企業買収の基礎知識(初心者向け)
企業買収について基本的な知識を身につけることで、今回のニュースをより深く理解できます。
💡 M&Aの仕組みと種類
M&A(企業の合併・買収)には複数の形態があります。今回の日立のケースは「事業売却」に該当し、企業の一部門を他社に売却する取引です。買収企業は対象事業の資産、負債、人材を引き継ぎ、事業を継続します。
🏦 買収価格の決定方法
買収価格は主に3つの方法で算定されます。資産価値に基づく「資産アプローチ」、将来の収益性を評価する「インカムアプローチ」、類似企業との比較による「マーケットアプローチ」です。通常はこれらを組み合わせて最終価格を決定します。
📊 買収による株主への影響
売却企業の株主にとって、事業売却は株価にプラスに働くことが一般的です。非効率な事業を手放すことで、残存事業の収益性向上が期待されるためです。また、売却資金の使途も株価に大きな影響を与えます。
🔍 買収ニュースの見極め方
買収ニュースを読む際は、買収目的、対価の支払い方法、統合計画、相乗効果の具体性に注目しましょう。これらの要素が明確で実現可能性が高いほど、投資機会として魅力的となります。
❓ よくある質問:読者の疑問に答える
読者から寄せられる疑問に対して、具体的で実用的な回答を提供します。
Q1. 個人投資家はどのタイミングで投資すべき?
A1. 売却の詳細条件が明らかになる10月頃まで様子を見ることをお勧めします。急激な株価変動に惑わされず、売却価格や資金の使途が明確になってから投資判断を行いましょう。ドルコスト平均法で少しずつ投資する方法も有効です。
Q2. 日立の他事業への影響は?
A2. 白物家電売却により、日立は電力、鉄道、ITサービス事業により集中できるようになります。これらの事業は高い利益率と安定したキャッシュフローを持つため、全体的な業績向上が期待できます。特にデジタル基盤「ルマーダ」の成長が加速する可能性があります。
Q3. 韓国企業による買収のリスクは?
A3. 技術流出や雇用への影響を懸念する声がありますが、過去の事例では大きな問題は発生していません。むしろ、韓国企業の先進的な技術やグローバルネットワークを活用できるメリットが大きいと考えられます。
Q4. 長期投資の観点で注目すべき点は?
A4. 日立の事業構造転換が成功すれば、10年後には現在とは大きく異なる企業になっている可能性があります。社会インフラとデジタル技術の融合により、新たな成長機会を獲得できるかが長期投資の成功のカギとなります。
Q5. 他の家電メーカーへの投資も検討すべき?
A5. パナソニック、シャープ、三菱電機など他の日本家電メーカーも業界再編の影響を受ける可能性があります。各社の戦略や財務状況を比較検討し、最も将来性の高い企業への投資を検討しましょう。
📚 関連して知っておきたい経済知識
日立の白物家電売却を理解するために必要な、より広い経済知識を提供します。
🌍 グローバル家電市場の動向
世界の家電市場は年率約5%で成長していますが、地域別では大きな差があります。アジア太平洋地域が最大の成長エンジンである一方、日本を含む先進国市場は成熟化が進んでいます。この市場構造の変化が、日本企業の戦略転換を促しています。
💼 産業構造転換の世界的トレンド
製造業からサービス業への転換は先進国に共通するトレンドです。日立の動きも、この大きな流れの一環として捉えることができます。物理的な製品よりも、ソフトウェアやサービスに価値の源泉が移行しています。
🏭 日本製造業の競争戦略
日本の製造業は、高付加価値製品や B to B 事業へのシフトを進めています。消費者向け製品では新興国との価格競争が激しいため、企業向けや社会インフラ向けの事業により活路を見出そうとしています。
📊 企業価値評価の新しい視点
従来の売上や利益だけでなく、データ活用能力やデジタル技術力が企業価値評価の重要な要素となっています。日立の「ルマーダ」戦略も、この新しい価値創造モデルの実践例です。
🛠️ 実践ツール:投資判断に使えるリソース
投資判断を行う際に活用できる、具体的なツールと情報源を紹介します。
📱 おすすめアプリ・サイト5選
- Yahoo!ファイナンス: リアルタイムの株価情報と企業ニュースを無料で確認できます
- 日本経済新聞 電子版: 企業分析記事と市場解説が充実しています
- Bloomberg: グローバルな視点での企業・市場分析に優れています
- EDINET: 企業の有価証券報告書など公式資料を無料で閲覧できます
- TradingView: 高機能なチャート分析ツールとソーシャル機能を提供します
📊 企業分析の基本指標
日立のような大型株を分析する際は、PER(株価収益率)、PBR(株価純資産倍率)、ROE(自己資本利益率)、営業利益率などの財務指標を確認しましょう。同業他社との比較も重要です。
📰 信頼できる情報源一覧
企業の公式発表、金融庁の EDINET、東京証券取引所の開示情報、大手証券会社のレポートなど、一次情報を重視しましょう。SNS や個人ブログの情報は参考程度に留め、必ず複数の情報源で確認することが大切です。
🎯 投資タイミングの見極め方
M&A関連の投資では、発表直後の急激な価格変動に注意が必要です。材料出尽くしによる調整を待つか、長期的な視点で段階的に投資することを検討しましょう。テクニカル分析と併用することで、より精度の高いタイミングを見極められます。
📝 まとめ:今日から始める3つのアクション
日立白物家電売却ニュースを受けて、投資家が今すぐ実行すべき具体的な行動計画を提示します。
✅ 今日やるべきこと
- 情報収集の開始: 日立製作所の公式発表と各種報道を確認し、売却の詳細情報を収集しましょう
- 現在のポートフォリオ確認: 日立株や関連銘柄の保有状況を確認し、投資戦略への影響を評価します
- 市場動向のチェック: 株価の動きと出来高を確認し、市場参加者の反応を把握しましょう
📅 今週中にやるべきこと
- 企業分析の実施: 日立の最新決算資料と中期経営計画を確認し、今回の売却がどう位置づけられるかを分析します
- 競合企業の調査: サムスン電子やLG電子の財務状況と戦略を調査し、買収の実現可能性を評価しましょう
- 投資資金の準備: 投資機会に備えて、資金計画を見直し必要に応じて調整を行います
🎯 今月中にやるべきこと
- 投資戦略の策定: 長期的な視点で日立への投資戦略を策定し、目標価格と投資期間を決定します
- リスク管理の見直し: ポートフォリオ全体のリスクバランスを確認し、必要に応じて分散を図ります
- 継続的な情報収集体制の構築: 今後の進展を追跡するための情報収集ルーチンを確立しましょう
参照元リンク
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました!
AI、暮らしのお金、世界経済の動向を、これからもわかりやすくお届けしていきます。「ちょっと気になるな」「朝の習慣にしてみようかな」と思ってもらえたら嬉しいです。
それでは、また明日のニュースでお会いしましょう☕現役プログラマー・チャチャがお届けしました!
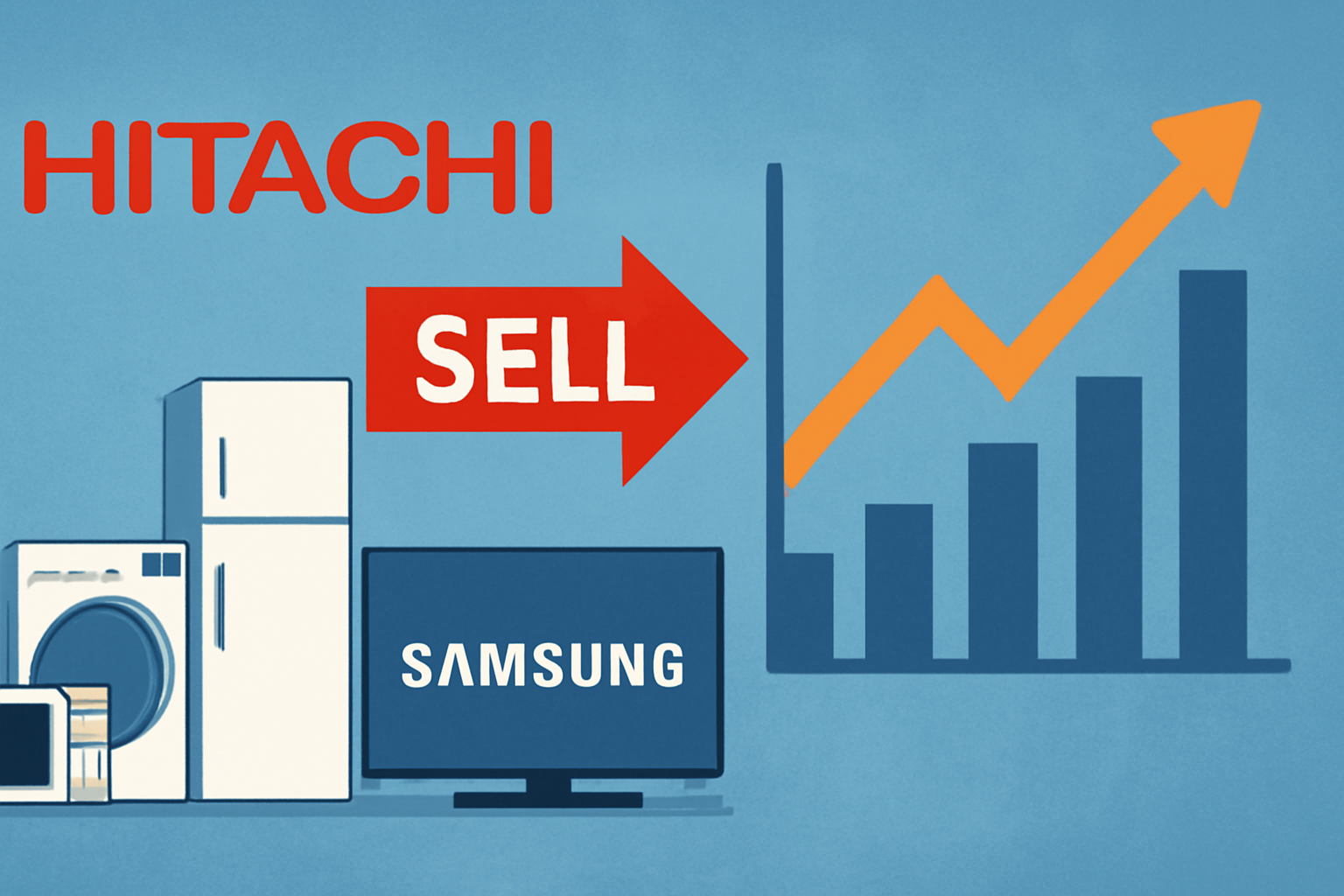

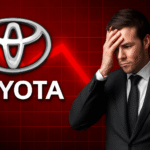

コメント