導入:年金改革の「大本命」――でも、誰も信じていない
「年金改革」と聞いて、どんなイメージが浮かぶだろうか。
「どうせまた先送り」「自分の老後にはもらえない」「制度が複雑すぎて分からない」――。
そんな国民の“ため息”をよそに、2025年春、年金制度改革関連法案が衆議院で可決され、参議院へ送付された。
「106万円の壁」撤廃、在職老齢年金の見直し、遺族年金の大幅改定、標準報酬月額上限の引き上げ、そして“積立金の流用”――。
どれも「聞いたことあるけど、よく分からない」テーマばかりだ。
今回は、この“気になるけど面倒”な年金改革の全貌を、皮肉と知的好奇心をスパイスに、徹底的に解体してみる。
📚マガジン紹介
「チャチャの解体新書|政治・お金・社会を読み解く知のスナック」
世の中の“気になること”を、ちょっと斜め上から真剣に、時には皮肉も交えつつ掘り下げるnoteマガジンです。
政治・社会・お金・テクノロジー・時事ネタなど幅広いテーマを扱い、日常のニュースや話題を一歩深く考察したい方におすすめ。
気になった方はぜひ、マガジンもチェックしてみてください!
👉「チャチャの解体新書|政治・お金・社会を読み解く知のスナック」
YouTubeチャンネルのご案内
「チャチャの解体新書」では、YouTubeチャンネルも運営しています。
記事で取り上げたテーマの解説や、動画ならではの分かりやすい図解、最新情報などを配信中です。
ぜひチャンネル登録して、最新コンテンツをお楽しみください!
今後も記事と動画の両方で、分かりやすく情報をお届けしていきます。ご意見・ご感想もお待ちしています!
背景と発端:なぜ今、年金制度改革なのか
少子高齢化という“無限ループ”
日本の年金制度は、もはや「昭和の遺物」と化して久しい。
少子高齢化、非正規雇用の増加、家族の多様化――現実は制度の想定を軽々と飛び越えていく。
5年に一度の「年金制度の見直し」も、もはや恒例行事。だが今回は、特に“106万円の壁”――パートやアルバイトが厚生年金に入りにくい年収要件――の撤廃が大きな柱となった。
社会の変化に追いつけない制度
- 非正規雇用の拡大:パートやアルバイトが全就業者の4割近くを占める時代に、年金制度が「正社員モデル」に依存し続けるのはもはや限界。
- 女性・高齢者の就労増:人生100年時代、老後も働くのが“普通”になりつつある。
- 年金だけでは食えない現実:65歳以上の生活保護受給者の7割超が年金受給者という皮肉な現実。
「年金だけじゃ暮らせない。でも働くと年金が減る。じゃあ、どうすれば?」という国民の“ため息”に、政治はどう応えたのか。
関係者と動き:与野党の珍しい“共闘”と、蚊帳の外の国民
今回の年金改革関連法案は、自民党・公明党の与党に加え、立憲民主党も修正案を共同提出し、衆院で可決された。
「政争の具にしない」などと美辞麗句を並べているものの、実際は与党が単独で通せない“少数与党”の苦しい台所事情が背景にあり、野党の協力なしには成立しないというギリギリの綱渡りだ。
一方で、日本維新の会や国民民主党など一部野党は「審議が不十分」「拙速すぎる」と批判し、反対票を投じた。
修正案の提出から衆議院での審議時間はわずか2日という“スピード可決”ぶりで、立憲の協力に他の野党からは「信じられない」「きばが抜かれた」などの猛反発が噴出。
国民民主党の議員からは「野党第1党が真っ先に与党と協議したことには強い違和感」との声も上がり、与党と立憲の“共闘”に対し「熟議されていない国会」と批判が集中した。
また、底上げに必要な財源の結論が先送りされたことや、一部の高齢者の年金が減る可能性があることも、反対理由として挙げられている。
さらに、法案の中身についても「“あんこの抜けたあんぱん”だ」「骨抜きだ」といった揶揄が飛び交い、与党・立憲ともに“あんこ”の詰め直しに必死。
自民党のベテラン議員からは「立憲案はのめる。向こうに花を持たせる形だが、選挙でうちも批判されないし、互いにとって良い結果だ」という本音も漏れ聞こえる。
「与野党の“共闘”と聞けば聞こえはいいが、実態は“妥協と打算の大連立”。」
「与党は“野党第一党の協力”という“免罪符”を手に入れ、立憲は“実績アピール”で存在感を演出。」
「他の野党は“裏切り者!”と叫び、国民は“またプロレスか”と白け顔。」
「“あんこのないあんぱん”だの“毒入りあんこ”だの、もはや国会は和菓子屋か毒見役か――。」
「結局、蚊帳の外に置かれたのは、いつも通りの国民。」
「“熟議の国会”どころか、“熟睡の国民”――年金の未来は、今日も政治家たちの“あんこ合戦”の中で、静かに遠ざかっていく。」
法的・政策的な攻防:何がどう変わる?――改正法案の中身を斬る
1. 「106万円の壁」撤廃――パート・アルバイトも厚生年金時代へ
これまで、パートやアルバイトが厚生年金に加入するには「年収106万円以上」「従業員51人以上の企業」「週20時間以上勤務」など、複数のハードルがあった。
今回の改正で「年収106万円」の要件が2026年をめどに撤廃。さらに企業規模要件も段階的に縮小され、2035年には「従業員5人以上」の企業まで対象が拡大される。
これにより、将来的に約180万人が新たに厚生年金に加入する見込みという。
- メリット:将来受け取れる年金が増える、健康保険の保障が厚くなる、年収を気にせず働ける。
- デメリット:社会保険料負担で手取りが減るリスク。特にパート主婦層には「働き損」感が根強い。
「壁を壊せばバラ色の未来なんて、どこかの不動産広告みたいな話だ。結局“壁”の向こうにも“崖”があるのが日本の社会保障。」
2. 在職老齢年金の見直し――「働く高齢者」にも追い風?
在職老齢年金制度は、一定以上の収入がある高齢者が年金を減額される仕組み。
今回の改正で、支給停止となる収入基準額を現行の月額50万円から62万円に引き上げ(2026年度施行予定)。
これにより、年金を受給しながら働く高齢者が、保険料負担に応じた本来の年金を受給しやすくなり、年金の減額を意識せず、より多く働けるようになる。
- 新たに約20万人が年金を全額受給できるようになる見込み。
「高齢者もバリバリ働いて納税してねというメッセージ。もはや“老後は悠々自適”なんて、昭和の幻想でしかない。」
3. 遺族年金の大改定――「男女平等」と「給付抑制」のせめぎ合い
改正前(現行制度)
- 女性の場合、夫が亡くなったとき「子がいない配偶者」の場合、30歳未満なら遺族厚生年金は5年間のみ支給、30歳以上なら生涯(無制限)で支給されていた。
- 男性の場合、妻が亡くなったとき55歳未満の夫は遺族厚生年金の支給対象外。55歳以上なら60歳から生涯受給できた。
- 子どもがいる場合や配偶者が60歳以上の場合は、年齢や性別にかかわらず生涯支給されていた。
今回の改正案(2025年以降)
- 子どもがいない現役世代(20代~50代)の配偶者が亡くなった場合、男女ともに「原則5年間の有期給付」となる。
- これにより、女性だけが年齢によって無制限で受け取れるという仕組みが廃止され、男女平等の制度設計へと移行する。
- 配慮が必要な場合(障害や特別な事情など)は5年以降も継続して受給可能な措置も設けられる。
- 現在受給中の人や40代以上の女性など、一定の年齢層には段階的な移行・経過措置が取られ、いきなり支給が打ち切られることはない。
- 5年間の有期給付期間中は、現行よりも増額された年金(有期給付加算)が支給される予定。
- 年収850万円未満という収入要件も撤廃され、支給対象が拡大される。
「男女平等と言えば聞こえはいいが、実態は“平等に痛みを分かち合いましょう”という話。」
「これまで一生もらえると信じていた人には寝耳に水。」
「“男女平等”の名のもとに、年金制度の“持続不能”をみんなで分かち合う時代がやってきた――。」
4. 標準報酬月額の上限引き上げ――「高所得者」もターゲットに
厚生年金保険の標準報酬月額の上限を、段階的に65万円から75万円に引き上げる(2027年9月から順次)。
高所得者の保険料・年金額の上限が引き上げられ、現役時代の賃金に見合った年金を受け取りやすくなる一方、保険料負担も増加。
「高所得者からも搾り取る――これぞ“平等”という名の再分配。だが、これで制度が持続するなら苦労はない。」
5. 基礎年金の底上げと積立金の流用――「3割カット防止法案」の舞台裏
修正案では、将来の財政検証で基礎年金の給付水準が一定以下に下がる恐れがある場合、厚生年金の積立金を活用して基礎年金を引き上げる措置を付則に明記した。
「現役世代の年金3割カット防止法案」とも呼ばれるが、裏を返せば“厚生年金の積立金を国民年金の穴埋めに使う”という、世代間・職種間の“玉突き”だ。
- 厚労省の試算では、現在40歳の女性が65歳から平均寿命まで受給する場合、295万円プラス。氷河期世代の50歳男性でも170万円プラス。
- 一方、現在63歳以上の男性や67歳以上の女性は現行より受給額がマイナスとなり、70歳男性では総額で23万円目減りする。
「積立金を流用と聞けば、会社員は思わず絶句。」
「自分が積み立てた年金が、他人の年金に化けるのかと不満も噴出。」
「世代間格差の是正か、現役世代の負担先送りか――“ツケの付け回し”は永遠に続く。」
6. マクロ経済スライド――「見えない年金カット装置」の正体
今回の年金改革でも“マクロ経済スライド”は温存されたまま。
これは、物価や賃金が上がっても年金の給付水準を抑制し、制度の持続性を維持する仕組みだ。
導入から20年で実質約1割、今後も10年以上でさらに10%削減される見通し。
- 共産党などは「マクロ経済スライドの停止」を主張し、現役世代・年金生活者のためにも給付抑制策の見直しを訴えている。
「年金カットとは言わず、調整と呼ぶ。言葉のマジックで痛みは消えない。」
7. iDeCo・企業年金の拡充――「自助努力」への誘い
iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入可能年齢を引き上げるなど、私的年金制度の拡充も進む。
「公的年金だけじゃ足りません。自分で備えてね」という、国の“やんわり突き放し”路線が鮮明だ。
「自助・共助・公助のバランス?――実態は自助8割、共助1割、公助は気休めくらいかもしれない。」
世界・各国の対応:年金制度は「日本だけの悩み」か?
年金制度の持続可能性は、先進国共通の悩みである。
ドイツやスウェーデンなどは「自動調整機能」や「積立方式」の導入で制度の安定化を図っている。
英国は基礎年金を税方式で一元化し、その上に報酬比例年金を乗せる“シンプルな一階建て”を実現。
一方、日本は「賦課方式(現役世代が高齢者を支える)」を維持しつつ、マクロ経済スライドなどで給付水準を調整してきたが、根本的な人口構造の変化には追いついていない。
「持続可能性とは、要するにどこまで国民の不満を我慢させられるかという壮大な社会実験。」
皮肉なことに、日本の年金改革は「世界に誇るべき迷走っぷり」とも言える。
「先送り」「小手先」「ツギハギ」――。
「失われた30年」の象徴として、年金制度は今日も迷走を続ける。
今後の展望:年金制度の「未来」はどこに?
年金制度の「未来」を語るとき、もはや「持続可能性」という言葉だけでは済まされないほど、現実は複雑で厳しい局面に差し掛かっている。ここでは、制度の根本的な課題と今後の論点、そして「本当に安心できる年金」を実現するために必要な視点を、さらに深掘りする。
1. 給付水準の低下と“底抜けリスク”
まず直面しているのは、年金給付水準の低下である。現行制度のままでは、将来的に年金の実質水準が今より2割程度下がると見込まれている。特に基礎年金の目減りが著しく、「老後の最低限の生活すら危うい」層が増える可能性が高い。
コロナ禍で少子化がさらに加速し、年金財政は一層厳しさを増している。給付水準の低下をどこまで縮小できるか――これが今後の最大のテーマである。
一方で、給付を維持しようとすれば保険料負担や税負担が増し、現役世代の生活を圧迫する。結局、「誰の痛みをどこまで許容するか」という“ゼロサムゲーム”が続くのだ。
2. 支給開始年齢の引き上げ論――「人生100年時代」の現実
世界に目を向けると、欧州では支給開始年齢を67歳以上に引き上げる国が増えている。イタリアでは71歳、所得代替率は87%という“老後の安心”が維持されているが、その分「長く働く」ことが大前提である。
日本でも、支給開始年齢引き上げは避けて通れない論点である。しかし政府は「選択制の繰下げ受給」などでお茶を濁し、抜本的な議論を避けてきた。
本気で持続可能な制度を目指すなら、「何歳まで働くのか」「何歳から年金をもらうのか」という社会的合意が不可欠である。現役世代が増えなければ、制度の屋台骨は揺らぎ続ける。
3. マクロ経済スライドの限界と“自動調整”の未来
日本の年金制度は、少子高齢化に耐えるため「マクロ経済スライド」という自動調整装置を持っている。現役世代の負担が青天井にならない代わりに、給付水準を自動的に下げる仕組みである。
しかし、これは「制度破綻を防ぐための最後の砦」に過ぎない。給付水準が下がり続ければ、年金の“生活保障機能”そのものが失われていく。
欧州では、支給開始年齢そのものを平均寿命に連動させる仕組み(デンマーク・オランダ型)も導入されている。日本も「給付額の自動調整」だけでなく、「支給開始年齢の自動調整」など、より抜本的な改革が求められるだろう。
4. 厚生年金の適用拡大と“働き方の未来”
今後の改正論点の一つは、厚生年金の適用拡大である。短時間労働者や小規模事業所の従業員も厚生年金に加入することで、低年金リスクを減らす狙いがある。
ただし、企業の事務負担や社会保険料負担の増加、非正規雇用のさらなる細分化など、新たな摩擦も生まれる。
「働き方の多様化」に制度がどこまで対応できるのか――この問いは、今後ますます重みを増すだろう。
5. 国民年金の納付期間延長と“現役世代の重圧”
基礎年金の拠出期間を現行40年から45年へ延長する案も議論されたが、「負担増」への反発から見送られた。
しかし、65歳まで働く人が増える中、納付期間延長は将来的な給付向上に直結する現実的な選択肢である。
「現役世代の負担をどこまで増やすか」「どの層にどんな恩恵を与えるか」――このバランス調整が、制度の信頼性を左右する。
6. 世代間・世代内の公平性――「分断社会」への警鐘
今後の最大のリスクは、年金制度が「分断社会」の温床になることである。
基礎年金の目減りが進めば、生活保護受給者が増加し、老後貧困が深刻化する。第3号被保険者(専業主婦等)の優遇や、高所得高齢者への給付など、世代内・世代間の不公平も放置されている。
「誰がどれだけ負担し、誰がどれだけ受け取るのか」――この根本的な問いに、正面から向き合う時が来ている。
7. 私的年金・自助努力へのシフトと“自己責任社会”
公的年金だけで老後を支えるのは、今や「都市伝説」に近い。iDeCoや企業年金の拡充、資産運用の推奨など、国は「自助努力」へのシフトを急速に進めている。
だが、低所得層や非正規雇用者に「自分で備えろ」と言われても、現実には限界がある。
「自己責任社会」の行き着く先は、格差の固定化と社会的分断――この危うさを直視する必要がある。
8. 政治の覚悟と「本気の改革」への期待
結局のところ、年金制度の未来を決めるのは「政治の覚悟」である。
支給開始年齢の引き上げ、納付期間の延長、給付水準の底上げ、負担の公平化――どれも痛みを伴う決断だが、これを避けていては制度の信頼は回復しない。
「100年安心」などというキャッチコピーに惑わされず、現実を直視し、国民的な議論を重ねること。
そして、制度の持続性だけでなく、「老後の安心」という本来の目的を見失わないこと――これが、年金制度の未来に必要な最低条件である。
「年金制度の未来は、国民の覚悟と無関心のせめぎ合いで決まる。」
「あなたは、どちらの側に立つか?」
深掘り:改革の“谷間”に取り残される人々
フリーランス・自営業者の苦境
今回の改正は「働き方の多様化」に対応とうたうが、実はフリーランスや自営業者にはあまり恩恵がない。
国民年金の水準は低く、iDeCoなど私的年金への自己責任が強調されるばかり。
「自分で備えろ」と言われても、低所得層には“備える余力”すらないのが現実だ。
氷河期世代・シングル世帯の行方
基礎年金の底上げは、特に非正規雇用が多い氷河期世代を直撃する。
「100年安心」と言われた制度が、実は“30年で3割減”という現実――。
シングル世帯や子どものいない世帯は、遺族年金や加給年金の縮小・廃止でさらに厳しい状況に追い込まれる。
企業・中小事業者の悲鳴
社会保険適用拡大は、中小企業にとっては「人件費爆弾」。
労使折半のルール見直しで企業負担が増す一方、助成金や経過措置も“焼け石に水”状態。
「働き方改革」と「経営の持続性」が激突する現場では、制度の理想と現実のギャップがますます広がる。
総まとめ――“安心”の幻想と、あなたへの問いかけ
年金改革関連法案――それは「安心の底上げ」か、「不安の先送り」か。
パートも厚生年金、積立金の流用、基礎年金の底上げ――どれも「現状維持」のための苦肉の策に過ぎない。
「改革」とは名ばかりで、実態は“ツギハギと先送り”の連続。
それでも、制度の持続可能性を高めるためには、どこかで「痛み」を引き受ける覚悟が必要だ。
「年金制度の持続可能性」とは、要するに「どこまで国民の不満を我慢させられるか」という壮大な社会実験。
「安心の底上げか、不安の先送りか――答えは、まだ誰にも分からない。」
あなたは、今回の年金改革をどう受け止めるか。
「自分には関係ない」と無関心を決め込むのか、それとも「老後の安心」のために何ができるかを考えるのか。
年金制度の未来は、あなたの選択と無関心の“積み重ね”で作られていく。
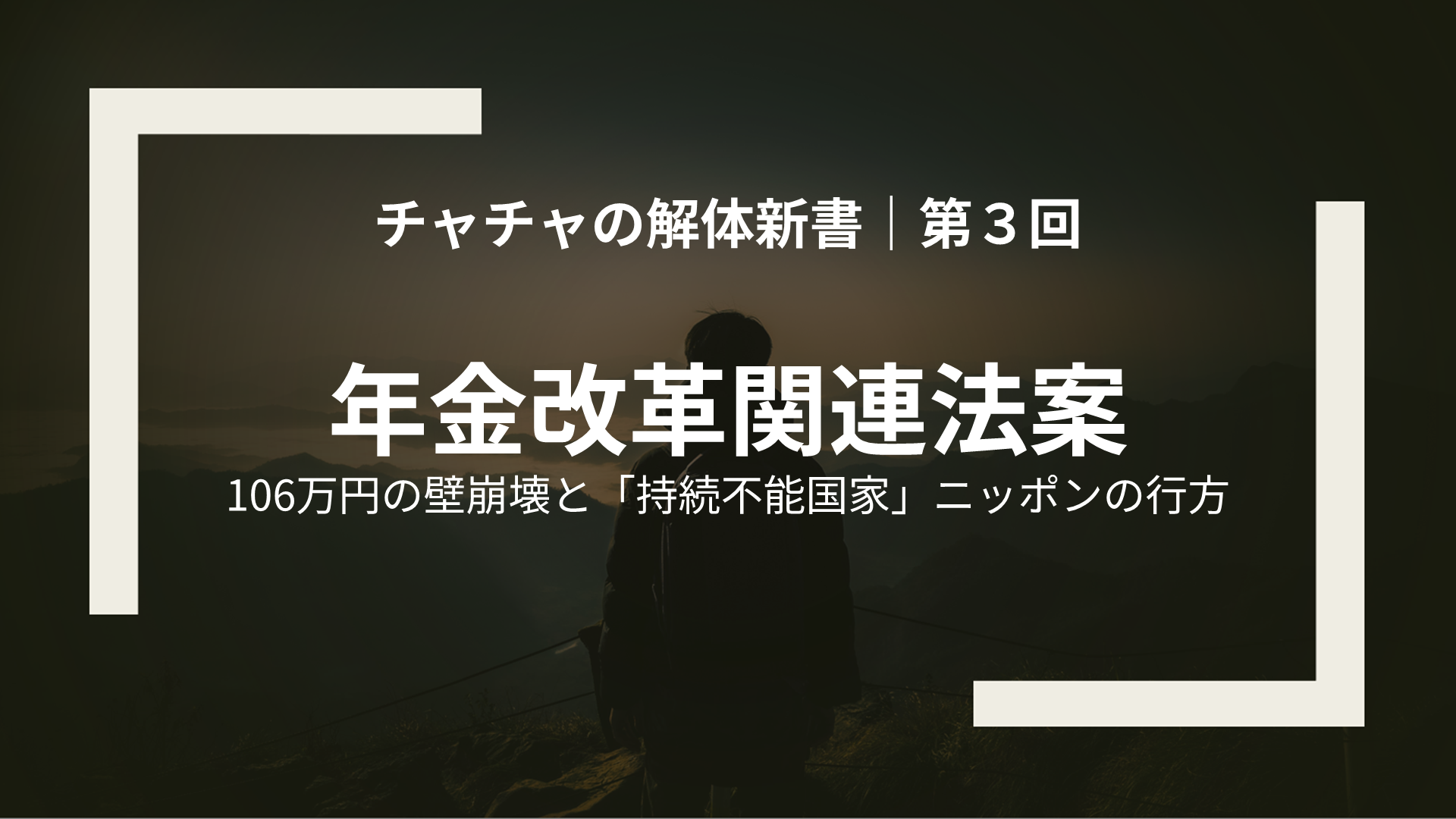

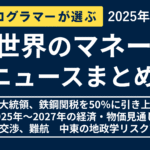

コメント